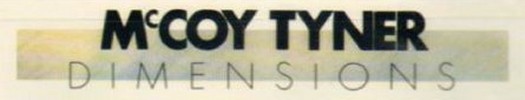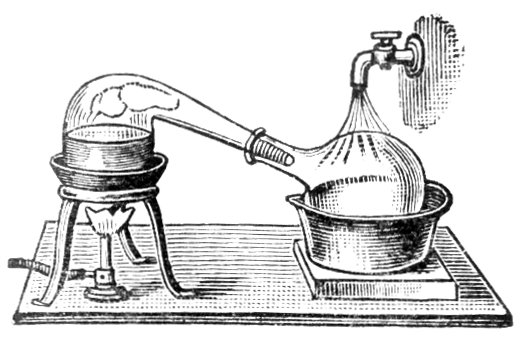View more presentations from Board of Innovation (BOI).
2010年に注目されたビジネスモデル・トップ10が話題になっている。10位にPatientsLikeMeが入っている。
Health2.0のビジネスモデルについてこのブログでも分析してきたが、現在見えているのはPatiensLikeMeやSermoのように、患者もしくは医師のUGCデータの再販ということになる。他にもあるはずなのだが、新しいビジネスモデルが医療関連ITビジネス創造のキイになることはまちがいないだろう。
広告、ユザー課金、モノあるいは情報商材販売などのレガシーモデルではないモデル。たしかにPLMはそう言う意味では新しいモデルではあるが、こんなビジネスモデル・トップ10に入るとは意外感が大きい。それほど医療関連ビジネスモデルが貧困であると言うことか。当方のdimensionsはいろいろな可能性を検討していきたい。これまでコンサルとパートナーを組み、マンパワーに頼った販売方法みたいなものを中心に描いてきたが、いかにもロウテクだし、もっと多様で柔軟な発想が必要だと昨秋から考えていた。まして「患者体験レポート」みたいなコンテンツを販売するなど、安易に考えていたこともあったもんだと反省。
ビジネスモデルのイノベーションこそ、Health2.0が成立する大前提だ。
三宅 啓 INITIATIVE INC.