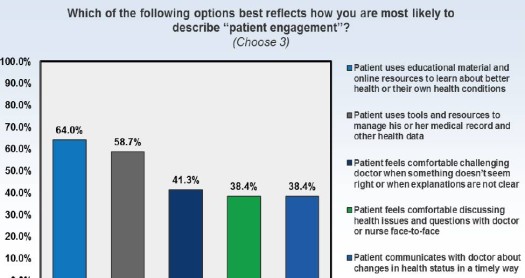前回エントリ「患者エンゲージメント」で「患者の感情の指標化」ということに触れたが、最近、このことをあれこれ考える機会が多い。特に私たちが注目してきた患者体験ドキュメントの基本性格というものは、「患者感情の表出」を抜きに考えることはできない。
私たちはこれまで、患者体験ドキュメントを患者が体験した「事実」を中心に見てきた。従来、どうしても「闘病記」という言葉で表されるドキュメントには、ある種の過剰な思い入れがつきまとい、それは時として「センチメンタルな物語」という形式に矮小化されてしまい、患者が体験した「事実」の客観的な意味を見失わせてしまいがちであった。
そうであるからこのブログでは、事実の連続体として患者体験ドキュメントを捉え、とりわけ固有名詞に注目し、なるだけセンチメントから距離をおくことを再三表明してきたわけだ。やがて、その成果はdimensionsというツールに実を結ぶ事になる。dimensionsは固有名詞をキイとして事実を抽出し集計するデータ・ツールである。 続きを読む