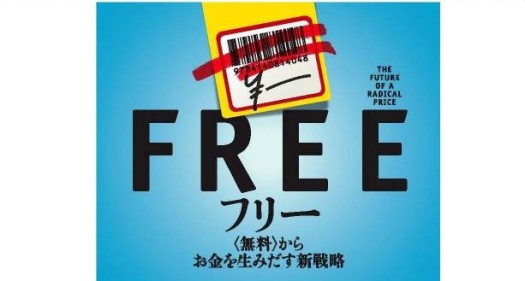今月でこのブログも開設三周年を迎える。いや、とにかく時間のたつのは早い。三年前の2006年12月のエントリタイトルを改めて見てみると、やはり「闘病体験の共有」や「闘病記の考察」など、TOBYOプロジェクトのコンセプトを固めるために書かれたものが多い。
これまで何度も書いてきたが、私たちはTOBYOプロジェクトにたどり着く前に、ピッカー研究所の調査メソッドをモデルに「患者体験調査」システム開発を模索していた。患者が実際に体験した事実に基づいて医療機関を評価しようと考えていたのだが、この「患者が実際に体験した事実」というものが、わざわざ新たに調査するまでもなく、既にブログや個人サイトの「闘病記」として大量に公開されていたのである。つまり調査システムを新たに開発する必要はなく、既にネット上に存在する体験ドキュメントを参照すれば済むことに気づいたわけである。
このように思い返してみると、私たちは最初から調査データという側面で闘病体験ドキュメントを捉えてきており、それは今日にいたるまで変わっていない。その後このブログでは、「闘病記」という括りで闘病体験ドキュメントを見ることから徐々に離れていくことになる。「闘病記」というリアルパッケージのメタファーでのみウェブ上の闘病体験を捉えるとすれば、新しい医療サービスの創造などは見えず、むしろ「闘病記」の評論や研究や出版サービスなどの方向へ進むことになっただろう。むろん、闘病記の評論や研究などは自由であり、否定するつもりはない。だが、私たちが進む道はそれらではないのだ。 続きを読む