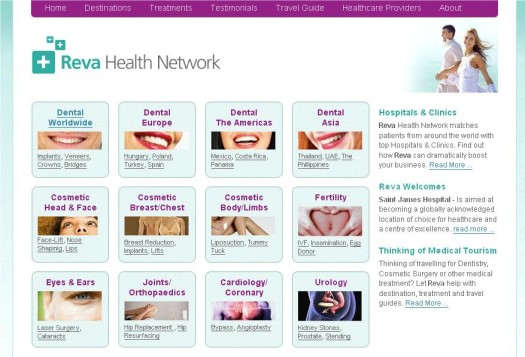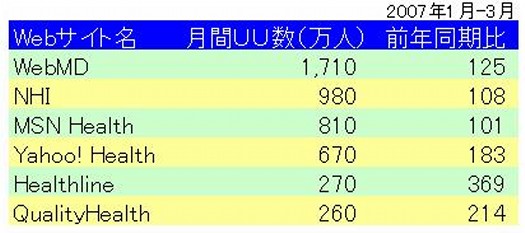先月、Vince Kuraitisがブログで展開したGoogle Health予想を紹介したが、その後、米国でこの予想をめぐる議論が巻き起こっている。議論は概ね次の二点に集中しているようだ。
1)私は、Google Healthの次世代PHR(Personal Health Records)を信じて、自分の個人医療情報を預けるべきだろうか?
2)Google Healthは本当に医療プレイヤーに採用され個人医療情報を共有することが出来るのだろうか?。なぜ、他のプレイヤーはGoogleと個人医療情報を共有しようとするのか、もしくは共有すべきなのか?。 続きを読む