一昨日(2月10日)の日経朝刊に、「乳がん患者、起業に動く。米国、闘病の経験、医療に生かせ」との記事が掲載されていた。
闘病生活の悩みから得たアイデアをきっかけに起業する乳がん患者の姿が米国で注目を集めている。「医療費を把握しやすいように」と開発したシステムや、着心地を改善した医療用衣類は「経験者ならでは」の工夫が施され好評だ。罹患率は日本の3倍以上の8人に1人。胸中は「不安を共有する別の患者に役立ちたい」という思いがにじむ。
(日経,08年2月10日) 続きを読む

一昨日(2月10日)の日経朝刊に、「乳がん患者、起業に動く。米国、闘病の経験、医療に生かせ」との記事が掲載されていた。
闘病生活の悩みから得たアイデアをきっかけに起業する乳がん患者の姿が米国で注目を集めている。「医療費を把握しやすいように」と開発したシステムや、着心地を改善した医療用衣類は「経験者ならでは」の工夫が施され好評だ。罹患率は日本の3倍以上の8人に1人。胸中は「不安を共有する別の患者に役立ちたい」という思いがにじむ。
(日経,08年2月10日) 続きを読む

患者による医療機関や医師のレーティング(評価、格付け)サイトは日本でも徐々に増えてきているが、もともとレーティング好きのお国柄である米国では、老舗のHealthGradesをはじめとしてかなり以前から多数のサイトが存在してきた。患者が医療機関や医師を選択する際の手がかりとして、これら医療レーティングサービスに対する期待はインターネット初期から大きかったのだが、最近、問題も指摘され始めている。
これら医療レーティングサイトはレーティング対象も評価手法も様々であるが、最近問題になっているのが、匿名ユーザーが医師一人ひとりを評価したレーティングデータを集計公開するサイトである。このスタイルのサイトとして有名なのがRateMDs。 続きを読む

先月6月、闘病体験共有サイト“CaringBridge”が開設10周年を迎えた。米国ミネソタ州を本拠とするこのサイトがローンチされたのは1997年。以来、患者と家族・友人のコミュニケーションを取り持つ無料サービスとして支持され、これまでに63000ページの患者ページを収録している。闘病体験共有サイトとしては、おそらく最初の世代に属するサイトである。 続きを読む
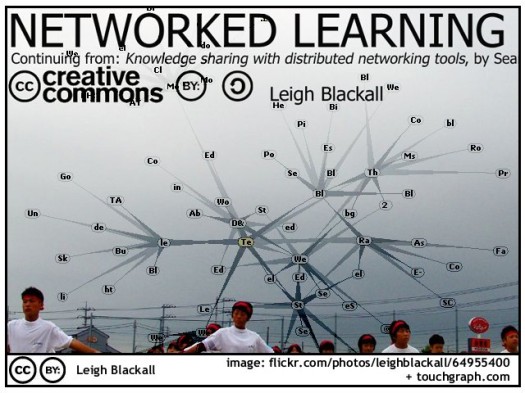
PGM (患者生成メディア:Patient Generated Media)
これまでこのブログでは闘病記の考察から始め、さらに広く医療IT化やWeb医療サービス、そして医療制度とその改革の問題までを論考してきた。闘病記は、以前の書籍版闘病記が近年ウェブ闘病記へと進化し、さらに日記形式という闘病記の原型を超えて、「闘病サイト」とでも言うべき情報拠点に変わってきていることを確認した。 続きを読む