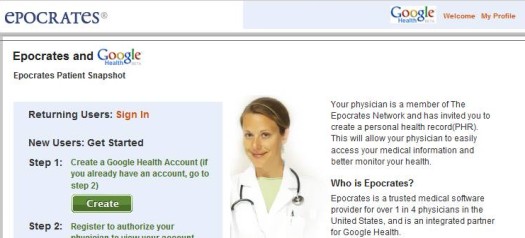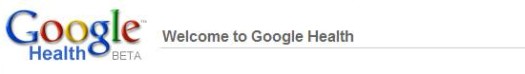(Microsoft Surface Demo for Patient Consultation (Interface by Infusion)
先日エントリでHealthVaultの家庭における利用イメージビデオを紹介したが、なぜかYouTubeから削除されてしまったようだ。その代わりと言っては何だが、PHRのもう一つの重要な利用シーンである医療現場における利用イメージを、やはりHealthVaultの紹介ビデオで見ておこう。
HealthVaultの医療現場での利用のために、マイクロソフトは「MS Surface」というアプリケーションを開発しているようだ。このビデオは医療現場で、この「Surface」を介して、医療者と患者がどのようにPHRの情報を利用できるかを紹介している。注目されるのはデスク上に平面設置されたディスプレイである。通常の縦置きディスプレイでは、医療者と患者の視線は平行で交わることがない。だがこのような平面設置ディスプレイなら、常に相手の視線を捉えながら、双方のコミュニケーションが可能となる。また、IDカードを画面上において読み取れるなど、操作性も良さそうだ。このSuefaceは、すでにテキサス州の医療機関”Texas Health Resources”で稼働しているとのことである。
続きを読む