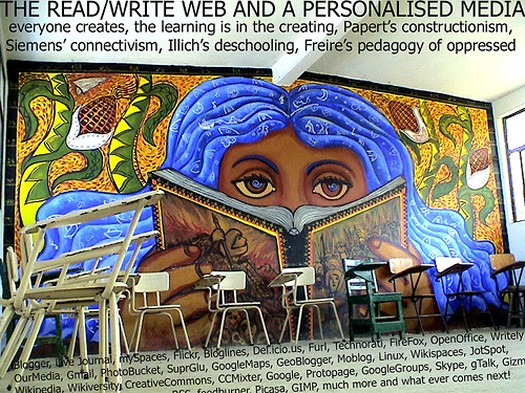以前から、当方がよく読んで参考にしているSteve Rubel氏のブログ「Micro Persuasion」に、“The Promise and Peril of Ubiquitous Community”というエントリがポストされた。来週号AdAge誌のコラムに掲載されるようだが、SNSを中心に近未来のウェブ進化を論じたものである。
このエントリでは、今日のSNSが実現しているようなソーシャル機能が、やがて「ウェブ全体のソーシャル化」によってユビキタス化される、というビジョンが提起されている。つまり、特定のSNSサイトを訪問することによって提供されているソーシャル機能やコミュニティ機能が、いずれ「空気を呼吸するように」、ウェブ上のどこにユーザーがいようとも、いつでも即座に利用できるようになるはずだと予測しているのである。 続きを読む