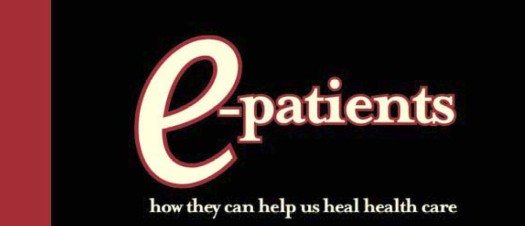まずは訂正から。先日エントリで、厚労省の資料から「日本の総患者数2,674万人」としたが、あとでよくよく考えてみれば、この資料はうつ病など精神疾患が抜けており、実際の総患者数はもっと多いはずだ。だがいずれにしても、闘病ユニバースの推定サイト3万件というのは全患者数から見て少ないことに変わりない。
昨日、TOBYO収録サイト数は1万7千件に達した。以前よりは収録ペースを落としているが、今後も収録数を増やし、いずれ闘病ユニバースの全体像をユーザーに提示できればと考えている。これまで過去に何回か「量的拡大の限界」ということを立ち止まって考え、「量から質への移行」など模索してきたこともあった。だが「推定3万件」という闘病ユニバースのサイズを考えてみると、十分に手の届くサイズであり、このまま全体像に近い規模まで収集を続けていきたい。 続きを読む