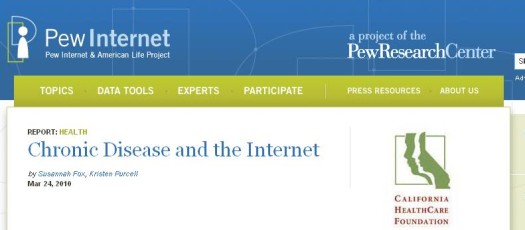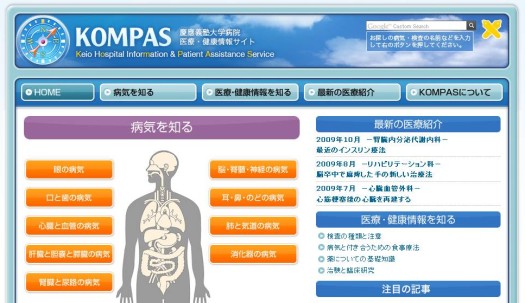3月も今日で終わり、早いもので明日からもう4月。TOBYOプロジェクトはここ3ヶ月の間、DFC商品化のための検討とテスト制作、そして検索エンジン「TOBYO事典」新規クロールの二つに取り組んできている。TOBYO事典は来月4月半ば頃にバージョンアップできる予定で、現在1万4千サイト300万ページの検索対象をさらに増量し、闘病体験可視化領域を拡大する。このように検索エンジン側の可視化領域が拡大すれば、DFCでハンドリングする解析データも増え、一層精緻に医薬品等の消費者体験&評価を提供することが可能となる。
DFC(Direct From Consumer)商品化だが、これは医薬品、医療機器、医療機関などを消費者体験から分析する”Fact Finding Tool”を目指している。たとえばある医薬品について、それを実際に体験した消費者の声を公開された闘病ドキュメントから集め、その医薬品がどのように消費者から体験されたかを分析する素材を提供するものだ。まだ詳細を公開できる段階ではないが、このDFCは大きく二つのパートから成る。 続きを読む