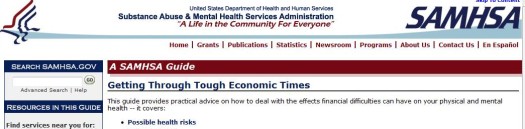このブログでは、おそらく日本で最も早く海外のPHRの動向を取り上げ、その意味を考察してきたと思う。そしてこの二年ばかりの間に、HealthVault、GoogleHealth、DOSSIAなど大規模PHRが登場してきたのだが、ではこれらが、未来の医療システムに一体何を持ち込むのかということについては、まだ不透明な部分が多い。だが、ここ二年ばかりの動きを注意深く観察してみると、PHR進化の道筋に沿って前方へと視線を投じることによって、未来の医療の姿形がおぼろげに透視できるような気がする。 続きを読む
カテゴリーアーカイブ: 医療
経済危機による精神疾患リスク
4月1日ワシントンポストによれば、米国政府のHHS(保健社会福祉省)は、今回の未曾有の経済危機プレッシャーによる米国社会の精神疾患増大に備え、ウェブで市民へ警告と情報提供を始めた。これはHHSのSAMSHA(薬物乱用・精神衛生管理庁)が運営するサイトに設けられたコーナーで、経済危機によってもたらされるリスクの警告、ストレス管理の方法、支援リソース、自殺徴候などについて市民に注意を促すものである。HHSがこのような精神疾患増大に対する警告キャンペーンをおこなうのは過去二回あり、一回目は2001年の同時多発テロ事件直後、二回目は2005年のハリケーン「カトリーナ」直後で、今回が三回目となる。 続きを読む
「サイト認証」という時代錯誤
医療関連ウェブサイトの国際認証団体であるHON(Health On the Net Foundation)が、その認証基本ガイドラインである「HONコード」の修正を計画している。HONはジュネーブに本部を置く国連の外郭団体で、最も権威のある医療サイト認証団体とされており、その認証シールは海外著名医療サイトはもちろん、医療ブログなどにも多数の掲出実績がある。
今回のHONコード見直しは、現在世界的に医療関連サイトにも浸透しつつあるWeb2.0サービスへの対応が主たる目的とされている。具体的には従来のHONコード8原則を土台とし、それぞれの原則をWeb2.0の動向に合わせ細かく修正している。この修正HONコード案はHONサイト上で公開されており、それに対するアンケートページも設けられている。
思い返せばインターネット初期、HONやURACをはじめいくつかの認証団体が立ち上がったが、結局、それらのうちで残ったのはHONコードだけと言ってよいだろう。それは他の認証ルールが煩雑を極めたのに対し、HONコードが「8原則」だけで一番シンプルだったからだと思う。日本でも「JIMA」とか「JACHI」などという団体が「サイト認証」に取り組んだが、まったく普及しなかった。 続きを読む
闘病ユニバースの可視化
今年は「世界天文年」の年らしい。たまたま、あるブログに貼られていたキャンペーンバナーを目にし、ようやく「世界天文年2009」の存在を知った次第だ。キャンペーンビデオもYouTube で見ることができる。ところでこのキャンペーンバナーだが、なんとなくTOBYOのシンボルイメージに似てるし、偶然とはいえ「闘病ユニバース」という考え方にも通じるところがある。
そのTOBYOだが、収録闘病サイトが14,000件を超えた。これで一応「国内最大級の闘病体験データベース」と言えるところまで来たわけだが、今後さらに収集を続けていきたい。これら多数の闘病サイトを収集整理する過程で、ウェブ上の闘病体験についてさまざまなことが徐々にわかってきた。たとえば、闘病体験を書きやすい疾患と書きにくい疾患があるらしい、ということである。おそらく患者数では最大であるはずの2型糖尿病だが、その闘病サイト数はむしろ少ない方だ。2型糖尿病の10分の1程度の患者数である1型糖尿病のサイトの方が、かえって多いくらいだ。ではなぜ1型が書きやすく、2型が書きにくいのか。このあたりは謎だが、なんとなくわかるような気もする。 続きを読む
頓挫したレセプト電子化・オンライン化
長年、日本医療の課題であったレセプト(診療報酬明細書)電子化・オンライン化だが、ここへ来て医療界からの猛反発に直面し先行き不透明になりつつあったが、結局、2011年に予定されていた義務化の実質骨抜きが決まったようだ。
政府・自民党は24日、具体的な治療内容や投薬名、診療報酬点数が書かれたレセプト(診療報酬明細書)のオンライン請求を平成23年度に完全義務化するとした政府方針について、新たに例外規定を設けることを決めた。この結果、23年度からの完全義務化は先送りされることが正式に決まった。
同日開かれた自民党の行政改革推進本部などの合同会議で、内閣府の規制改革推進室が、例外規定の設置方針を含む「規制改革推進3カ年計画」の改定版を提示し、了承された。(産経ニュース2009.3.24)
レセプトデータの電子化は、医療費のムダを抑制し、医療の効率化を促進する基礎となる施策であるが、またもや先送りされてしまったわけである。費用の可視化および透明化は、すべての経済活動の前提的基礎であるが、なぜ医療だけが除外されるのか。今回、レセプト電子化に反対した日本医師会、歯科医師会、薬剤師会は、消費者に納得のいく説明をすべきであろう。これについて「地域医療の崩壊が促進される」などというわけのわからないロジックが出されているのだが、このような稚拙な説明は消費者を愚弄するものだ。 続きを読む