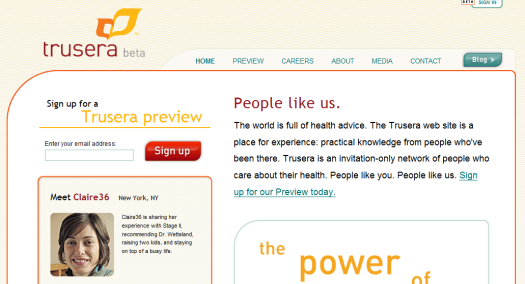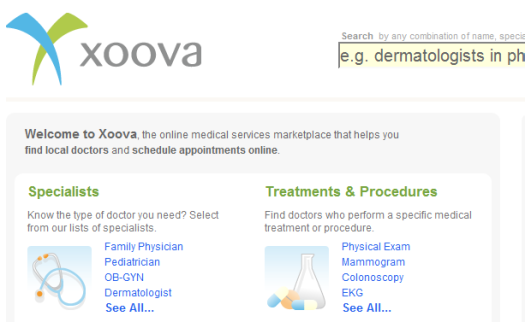先週のTecCrunchで「検索結果を信用していない人が増加中」というエントリーがポストされた。南カリフォルニア大学のデジタル未来センターの調査レポートが元ネタなのだが、Googleなど検索エンジンの検索結果に対する信頼度が低下しているというのだ。
この調査から、検索エンジンの情報を信用している人がわずか51%しかいないことがわかった。これは2006年の62%から減少している。Googleは米国で最も利用されている検索エンジンだが、半数近く(49%)の利用者はGoogleを信頼していない。この結果は興味深い。(TecCrunch Japan, 2008年1月18日)
たしかに汎用検索エンジンが提示する検索結果はゴミ情報が多く、膨大な「情報の海」から求める情報を選択吟味するのは容易ではない。だから、一般的にすべての検索結果を信頼できるわけがないし、むしろ個々の情報に対し猜疑心をもって臨むのは当然である。となると、検索結果に対する信頼度低下を一概にネット全体への不信感の増大と見ることはできず、逆に健全なネットリテラシーが定着してきている証左として見るべきだと思える。 続きを読む