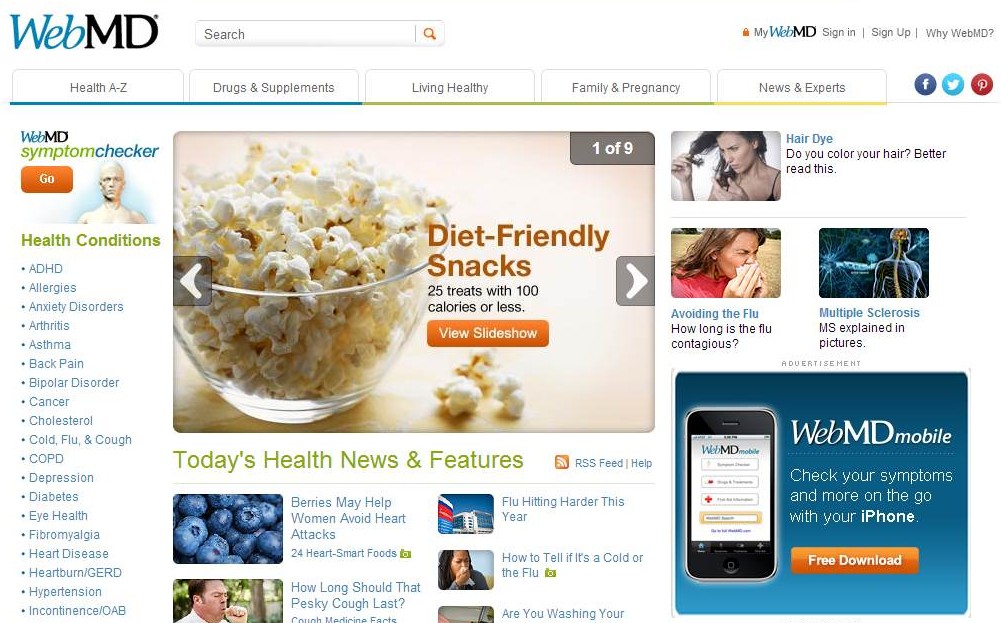最初の選択
私たちのTOBYOプロジェクトは、ネット上にすでに公開されている闘病ドキュメントに着目するところからスタートした。闘病ドキュメントを集める方法としては、患者コミュニティを作り、そこで闘病記を書いてもらうというのがむしろ一般的だろうが、私たちはそうではなく、「すでにネット上に存在するドキュメント」を活かす方法はないかと考えたのである。当然、「これからコミュニティを作り、ユーザーを集め、書いてくれるのを待つ」よりも、「もう既に書かれて公開されているものを集める」ほうが確実でしかも早い。つまり最初の段階で、私たちは「コミュニティを作る」という発想を捨て去り、もっとも容易でシンプルな方法を選択したことになる。経営リソースの乏しいベンチャー企業にとって、「あれも、これも」という贅沢な選択をする余裕はない。「あれか、これか」と取捨選択を徹底し、自分たちの在り様をできるだけシンプルでスリムにしておくことが求められるのだ。
その結果として、TOBYOプロジェクトは4万件の収録サイト数達成を目前にしている。これはおよそ5万件と推定される闘病ユニバースの8割をカバーする規模であり、TOBYOは文字通りネット上の最大の闘病ドキュメント・ライブラリーに成長することができた。今後も規模の拡大を継続し、初期のミッション「ネット上のすべての闘病ドキュメントを可視化し、検索可能にする」を遂行することにかわりはないが、プロジェクトはさらに新たなミッションを帯びた新規の活動段階に来ていると考えている。それは4万サイトに蓄積された500万ページのデータを読み取り、そこに隠された意味を探索し、そこから患者の感情と一般意志を抽出し理解することである。