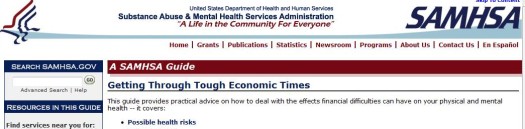米国で、最もユニークで、最も成功している患者SNSと言われるPatientsLikeMeだが、今月、そのフラッグシップコミュニティである難病ALS(筋萎縮側索硬化症)コミュニティの設立三周年を記念し、新たに「遺伝子検索エンジン」サービスの開始が発表された。これはALS患者が、遺伝子レベルで「自分と似た患者」を探すことができるようなサービスであるとのこと。また、同コミュニティ患者の遺伝子情報を共有することにより、ALSの原因と結果の解明をはじめ、新しいALS治療法の開発などに活かすことができるとしている。
Google資本の23andMeをはじめ、一昨年あたりから消費者向け遺伝子解析サービスが多数立ち上がってきたが、いよいよこの流れが患者SNSと合流し始めたわけだ。23andMeもコミュニティを形成しようとしているのだが、PatientsLikeMeの場合、データ共有の目的が、たとえば「ALSの新治療法開発」などと非常に明確になっているだけに、説得力あるユーザーメリットを打ち出せるのではないか。このあたり、PatientsLikeMeの巧みなターゲット戦略には学ぶべきものが多い。 続きを読む