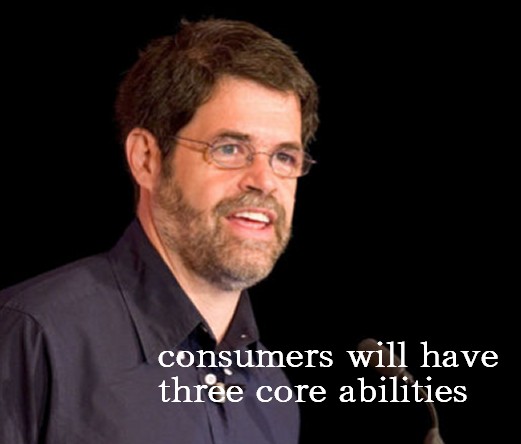一昨日のエントリ「医療情報システムの三つの顔」に対して、ganfighterさんが各システムの英語定義を翻訳してくださった。あらためて感謝しておきたい。またynbさんから、各システムの定義について素晴らしい考察をしていただいた。これも感謝しておきたい。なるほど、「データの網羅性」という基準を立てると各システムの差異は一層明確になるはずだ。その際、たしかにEMRは医療現場に一番近いシステムであるだけに、最も広範な「データの網羅性」を持つことになる。かたやPHRは、患者に最も近いシステムとして「患者自身による訴えの記述」までをカバーできる。そうなるとEHRが中途半端な立場に立たされそうだが、ynbさんが言われるように、そのデーターカバレッジは「パブリック」という観点から限定される可能性は高いだろう。だが、そうなるとEHRの経済的基盤はどうなるのだろうか。 続きを読む
カテゴリーアーカイブ: PHR
医療情報システムの三つの顔(EMR、EHR、PHR)
最近、米国でNAHIT(National Alliance for Health Information Technology)が発表した「EMR、EHR、PHRの定義」がちょっとした話題になっている。なるほど考えてみると、これまでEMRとEHRの差異さえ実は明確ではないうちにPHRが出てきてしまったので、これら三者の関係があいまいなままに放置されているような現状がある。NAHITによるそれぞれの定義は下記のようになっている。
EMR:
The electronic record of health-related information on an individual that is created, gathered, managed, and consulted by licensed clinicians and staff from a single organization who are involved in the individual’s health and care.
EHR:
The aggregate electronic record of health-related information on an individual that is created and gathered cumulatively across more than one health care organization and is managed and consulted by licensed clinicians and staff involved in the individual’s health and care.
ePHR:
An electronic, cumulative record of health-related information on an individual,drawn from multiple sources, that is created, gathered, and managed by the individual. The integrity of the data in the ePHR and control of access to that data is the responsibility of the individual.
「未来の別の顔」:個人医療情報をめぐる近未来シナリオ
一昨日のエントリ「量から質へ」で述べたように、闘病サイトの可視化がある程度量的に達成された後、次にTOBYOは提供するサービスの質的充実を図っていく必要があると考えている。それはおそらく「闘病体験情報の構造化」を進める方向で充実をしていくような、そんなイメージを今の時点では持っている。要するに、闘病者が知りたい情報をより適切に、そして一層簡単に利用できるようにするわけだが、まだ具体的な方法を提示する段階には至っていない。
われわれは、TOBYOを開発するためのビジョン策定をこのブログでさまざまな方向から試行してきたのだが、ようやく「闘病ネットワーク圏」という考え方にたどり着いたのである。この「闘病ネットワーク圏」に対し「いかなる役割を果たすべきか」というふうに問題を提起すると、TOBYOの立ち位置を非常に明確に理解することができたのである。すなわち、「闘病ネットワーク圏」という形で分散展開され膨張してきた闘病体験のゆるいネットワークを、ことごとく可視化することがTOBYOの果たすべき役割となった。 続きを読む
ビジョン不在の医療情報化論
一昨日のエントリで、PHRに対する当方の当面の関わり方について述べた。もちろん医療システム全体における中心的役割を、今後PHRが果たしていくことはまちがいない。だが、この春発表された「日本版PHRを活用した健康サービス研究会」(経産省、厚労省、総務省、内閣官房)の総括報告書を読んで、本来のPHRがどのように矮小化されてしまうかを目の当たりにして、失望を禁じ得なかったのである。この研究会とその報告書に対する当方の批判は、こっちのエントリにまとめてある。
その後、「日本におけるPHR」の動向には全く関心がなかったが、一昨日エントリを書いてからGoogleで検索してみると、いくつか関連する出来事が浮かび上がってきた。どうやら「健康情報活用基盤構築のための標準化及び実証事業」というプロジェクトが経産省主導で動き出している模様である。ざっと目を走らせると、「やはり」と言うべきか、「またしても!」と言うべきか・・・とにかくこの種の官庁プロジェクトでは「お決まり」の「公募コンソーシアム」が募集・決定されている。予算は7億円で4つの「コンソーシアム」が決定済み。かつて数年前、厚労省がこの種の「健康関連市場開発コンソーシアム」を多数募集し実施していたが、結局、事業化にたどり着いたものは一つもなかったと記憶している。また個々の「実証実験プロジェクト」の結果がどうであったかも、一向に定かではなかった。果たして公表されたのか?。だが今回、経産省はじめ関係者諸氏は、きっと「結果責任」を取ってくれるのだろう。 続きを読む
日本のPHR(Personal Health Records)について
最近、PHR(Personal Health Records)について意見を求められることが多い。たしかに、日本語のまとまったPHR情報を探してもこのブログぐらいしかソースがない。そこで当方に問い合わせをしてみよう、ということなのだろう。以前はそれらの問い合わせに応じて、当方で把握している情報を提供したりすることもあったのだが、最近はこの種の問い合わせには対応しないようにしている。この場を借りて、問い合わせをされて来られる方々には不義理をご容赦願いたい。
まず、当方はPHR評論家でも研究者でもない。昨年来、Google Healthを中心にPHRに関するエントリはずいぶん書いてきたが、それらも新しい医療サービスを考える手がかりや教材として、また純粋に当方の思考実験材料に利用したにすぎないのである。それに、情報ソースもすべてウェブ上に公開されているものばかりであり、特別な取材源を持っているわけでもない。だから、誰でもすこし丹念に調べるつもりさえあれば、フィードリーダーなどを活用して必要な情報を好きなだけすぐさま集めることができる。中には「リンクやOPMLまで提供してほしい」というご要望を頂戴することもあるが、そこまで当方が手取り足取りして面倒をみるわけにも行かない。どうかご自分でお探しいただきたい。また、もちろんこのブログで利用できるところがあれば、どんどん使ってもらって結構である。 続きを読む