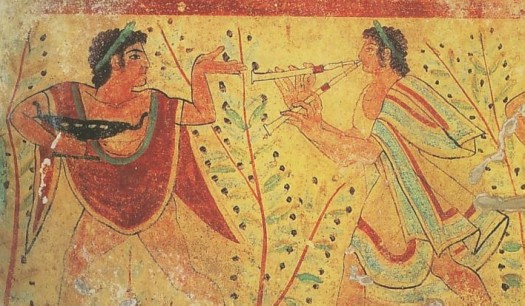ご報告が遅れたが、5月8日付け毎日新聞「関心高まる闘病記:下 先輩患者の知恵、ネットに」にTOBYOが紹介された。実はこのブログで紹介するかどうか、少し迷った。というのは、また例によって「Dipex Japan」という団体の紹介がメインで、記事の半分強を占め、TOBYOやライフパレットは「刺身のつま」みたいな扱いでお茶を濁されていたからだ。まだ実際に何のサービスも開始していないにもかかわらず、なぜだか毎日新聞はじめマスメディアはこの団体にご執心である。
だが、以前から疑問だったのは、オックスフォード大学から始まったとされるこのDipexが、Health2.0など海外の新しい医療シーンでは、まったく話題にも上がっていない点だ。私は2005年くらいから、海外の新しい医療ITの動向をウォッチしてきたつもりだが、この「Dipex」関連のトピックスやニュースに触れたことは一度もなかったのである。だが、当方の見落としということも当然あるだろう。というわけで「Dipex」の本家本元の英国サイト「healthtalkonline.org」を調べてみた。 続きを読む