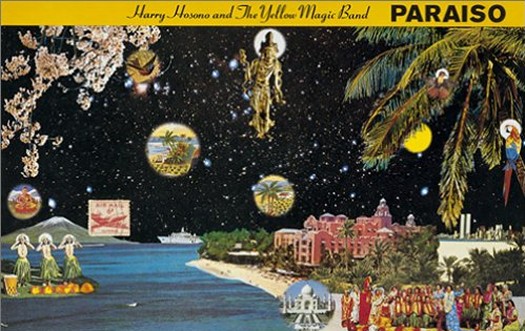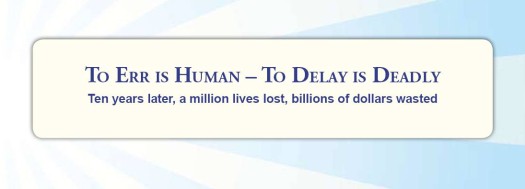ずいぶん時間はかかったが、TOBYOプロジェクトは闘病ユニバースのうち約1万6千件の闘病サイトを可視化し、「1万人が書いた闘病記の全文検索」を実現するところまで来た。もちろん今後も、引き続き闘病ユニバースの可視化件数を増やし、検索精度の向上に努めていかなければならないのだが、実は次のステップについてもビジョンづくりを進めている。
まだボンヤリしたイメージに過ぎないし、言葉としても練れていないのだが、次に私たちが取り組むのはおそらく「闘病情報の標準化」というテーマになると思われる。現在、TOBYOプロジェクトが取り組んでいるのは、ウェブ上に分散する不定型な闘病体験情報を分類整理し検索可能にすることだ。このことによってはじめて、自発的に形成された闘病ユニバースにすでに存在する膨大な量の体験情報が、誰にでも簡単に活用できるようになる。だが、これら闘病体験情報は不定形であるがゆえに、相互に比較しにくく、統計処理もしにくいような定性的データである。つまり「個別闘病者の個別体験」という自己完結性を強く持ち、それらを横断的に比較参照して「何かについての評価をおこなう」ようなデータではない。この際の「評価」とは、まず端的に言って「医療機関評価」ということになるだろうが、さらに「医療者、治療法、薬剤、医療費の評価」へと展開されるだろう。 続きを読む