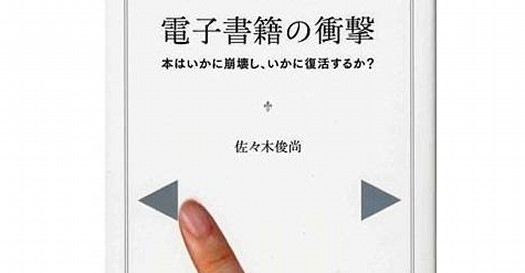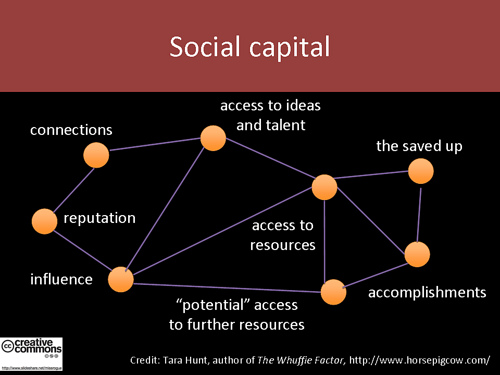現在のTOBYOプロジェクトの焦点はネット上の闘病記録すなわちデータにあり、もはやパッケージとしての「闘病記」に対する強いこだわりはない。いわゆる闘病記パッケージに関することは、闘病記屋さん達に任せればよい。そう考えている。
それでもキンドルやiPadの出現によって電子書籍が現実のものになってみると、パッケージとしての闘病記をめぐる状況もこれまでとは大きく変わってきている。闘病記を出版したいと考えている人達にとって、自分の闘病記を出版しマネタイズするチャンスが訪れているからだ。
「電子書籍の衝撃」(佐々木俊尚、ディスカバー携書)は電子書籍の現下の状況をレビューしつつも、その背景をなす文化的、社会的イシューに目を配り鋭い考察を提出している。本論ではないが、脇に周到に配された記号消費終焉論などもたいへん面白く読めた。さて、本書第三章「セルフパブリッシングの時代へ」だが、ここで紹介されている方法で、近々日本でも闘病記をセルフパブリッシングする人が出てくるだろうと思った。 続きを読む