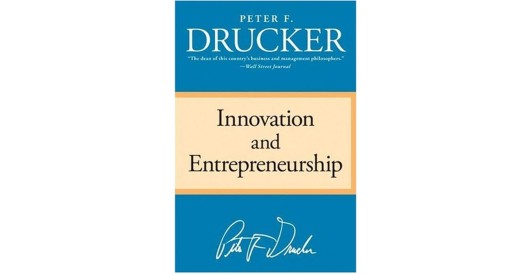昨夜の「孫正義vs佐々木俊尚 徹底討論『光の道は必要か?』」は面白かった。夕食後、8時過ぎからUstreamで見始め、結局12時までお付き合いしたのだが、トークセッションが終わったのは深夜1時だったらしい。なんと延々5時間。このセッションの概要は「光の道 テキスト中継ログ #hikari_roadhttp:」ですべてテキスト化されている。
全体を通してみれば、両者の議論は咬み合うように見えながら微妙にすれ違っていた。どこですれ違っているかといえば、インターネットの現状と将来をめぐる孫氏のハード・インフラ至上論と佐々木氏のプラットフォーム優位論においてである。たしかに全国津々浦々に国費ゼロで「光の道」を整備できれば、それはそれですばらしいだろう。だがそのことによって、自動的に日本のインターネットが飛躍的に活性化されるかといえば、そうではないだろう。今日、われわれが実感しつつある日本のインターネットをめぐるある種の閉塞感と言うものを考えると、それはインフラが光かメタルかという問題とはまったく次元が違うと思う。
「インターネットを使わない」理由だが、これを見るとネットの普及が進まないのは料金の問題よりも他の要因の方が相対的に大きいことがわかる。つまりは固定回線のネットを利用することにさほど魅力が感じられていないのだ。もちろん都市部のデジタルネイティブな国民の間では、ブログやTwitterなどのソーシャルメディアやさまざまなリッチコンテンツを楽しむ文化ができあがってきているが、しかしたとえば地方の高齢者などにはそういう文化は比較的伝わりにくい。本来そうした層に送り込むべきインターネットのサービスは、たとえば健康管理やセキュリティといった、もっと生活に密着したサービスだ。
(「ソフトバンクの「光の道」論に全面反論する(下)」 佐々木俊尚)
最近、「日本の医療ウェブの成熟度」ということを考える機会が多いのだが、たしかに日本の医療インターネット分野において、生活に密着した便利な医療サービスの数は驚くほど少ない。欧米に比べると、日本のインターネット医療サービスの貧困という現状は否定できない。そしてこのことは「光の道」の達成、つまりインフラ整備の問題とはほとんど無関係である。 続きを読む