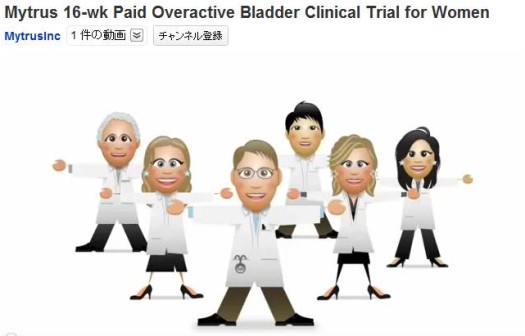昨年から、あちこちで「ゲーミフィケーション」という言葉を目にする機会が増えてきている。この言葉を手っ取り早く理解すると、以下のようになる。
ゲームデザイン手法や仕組みを用いて問題の解決やユーザー契約などを獲得すること。例えば、既存のシステムやサービスへの、ポイント性、順位の可視化、バッヂ、ミッション、レベルシステムの採用など。さらにゲームの要素を盛り込むことによって楽しみながら意図せずそれらと関わっていってもらうことが目的で行われる場合もある。(wikipedia:ゲーミフィケーション )
このゲーミフィケーションの手法を医療Q&Aサービスに導入したのがHealthTapである。このサービスが普通の医療Q&Aと異なる点は、ゲーミフィケーションの仕組みを回答者である医師参加者に適用している点にある。
HealthTapに参加した医師は謝礼や換金可能ポイントなどは与えられないが、そのかわり回答数、医師同士の”agree”評価、一般ユーザーの”thanks”評価などのポイントを競い、獲得ポイントによってさまざまな「賞」を贈られたり、自己の評価ステータスを示す「レベル」を上げたりすることができる。
また、HealthTapでは医師の参加モチベーションを上げるために、以上のようなゲームライクな競争の仕組みを用意するのみならず、医師個人を可視化し、ウェブ上の医師プレゼンスを高め、同じ地域の患者への認知促進をはかるなどの「販促効果」もあるとしている。これらの「メリット」にひかれてか、現在、医師参加数は約9000人を数え、毎日100人づつ増加しているとHealthTapは発表している。 続きを読む