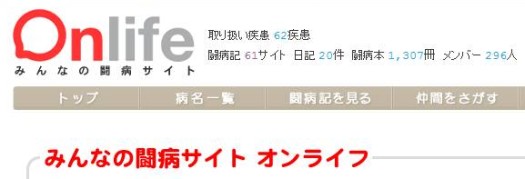今週月曜日(8月3日)から、消費者商品評価団体ConsumerReportsは全米病院のレーティングサービス を開始した。この病院レーティングは、米国政府が実施している「患者体験に基づく病院評価調査プロジェクト=HCAHPS(the Hospital Consumer Assessment of Healthcare Providers and Systems)」のデータを利用し、消費者にわかりやすい形で提供しようというものだ。全米約3700病院で、約100万人の患者が入院中に実際に体験した結果を、以下に見るHCAHPSの「8つの評価指標」について集計分析している。
- 医師や看護師とのコミュニケーション
- ペインコントロール
- どの程度の頻度で、必要な時の呼び出しに対応されたか
- 病室の清潔さと静かさ
- 新薬についての情報
- 退院時の説明
- その病院を家族や友人に推薦するかどうか
- 総合的な入院体験評価
HCAHPSとは懐かしい!。数年前、当方は医療評価事業を構想しており、当時このHCAHPSや英国CHI、またこれらのルーツであったピッカーメソッドを徹底的に研究していたことがあった。HCAHPSは、当時のブッシュ政権の医療政策における目玉の一つであり、「一つの統一尺度で全米病院を患者視点で評価し、消費者の病院選択に役立てる」ことを目指す先進的なプロジェクトであった。だが「先進的」であるが故に、医療界、レガシー調査ベンダー業界などの抵抗は根強く、調査票開発などは何度も挫折を経験したのである。 続きを読む