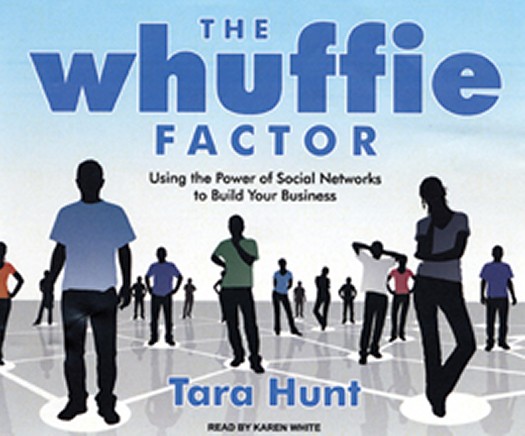ここ二三日、必要があっていくつかの病院サイトをあれこれ調べている。病院サイトのつくりだが、以前よりはだいぶ改善されたように見えるが、まだまだサイト内導線やUI、情報配置などユーザーに対する配慮は不足していると言わざるを得ない。特に初診案内のわかりにくさは致命的だ。病院で診察を受けようと初めて訪ねてきたユーザーに、もう少していねいな気配りがあってもよいのではないか。特に診療日時や受付場所など、きわめて基本的な情報が不備であるケースが多いのだ。それに対して、相変わらず院長挨拶とか病院理念などを麗々しく配置しているのを目にすると、医療機関のコミュニケーション・マインドはまだまだ低いと言わざるを得ない。
医療機関ウェブサイトの品質を上げることは、依然として大きな課題である。たとえば「ユーザーが選ぶわかりやすい病院サイト、ベスト100!」などコンテストを設けてみるのもよいかも知れない。TOBYOで病院サイト評価&投票を呼びかけてみようかとも思う。医療評価の一環として、もうすこしサイト評価が注目されても良いのではないか。 続きを読む