タラ・ハント「ツイッターノミクス」のエントリをポストしたら、早速この本の編集者の方からコメントをいただいた。このスピードにまず驚いた。ブログにツイッターが加わることで情報伝播スピードは猛烈に加速される。このことを実際に体験してみると些末な閉塞感などは忘れ、いかにこの私たちの時代がわくわくする時代かと思えるのである。
TOBYOプロジェクトもこんなスピード感を何らかのかたちで導入したいものだ。いずれにしても、やがて多くの闘病者が自分の闘病体験をツイッターでリアルタイム配信する日がやって来るだろう。すでにそれは一部では始まっているだろう。そして、たぶん従来のような起承転結を持つ「物語」を語るのではなく、自分がいま知りたいことをリアルタイムに誰かへ向けて問うようなスタイルになると思われる。自分の体験を自己完結的に語るのではなく、自分が直面する現下の問題を誰かに問うことへと、ユーザーの情報配信行為は変わっていくと思う。ここでクラウドソーシングがどのように機能するかは興味深い。
従来は闘病というきわめて個人的問題に閉じていた分野が、今後、そのソリューションをめぐってソーシャル化されていくことは間違いないと思われる。その先行事例がPatientsLikeMeであり、難病に立ち向かうのに個人体験のみでは圧倒的に非力であり、出来る限り多くの体験者とのコラボレーションが必要になるのである。現在進められている「1万人のパーキンソン病コミュニティ」はそのような発想によるプロジェクトだ。
ところでツイッターの医療における使われ方として、医師が直面している問題をツイートしオープンに投げかけ、それに対しリアルタイムで世界中の医師が知識や経験を提供するということがすでにあちこちで起きている。同様に、すでに生起した事実を語るのではなく、今、選択に迷っている問題をオープンに投げかける患者が増えてくるだろう。つまり、これからは「体験を語る」よりも、目前の医療選択などリアルタイム意志決定領域でツイッターなどが活用されると思う。「起きてしまったこと」に対してではなく、「これから起きる可能性のあること」に対しどう対処するかを問うツールとして、一層ソーシャルメディアが活躍するような気がする。
だから「闘病体験の共有」と言っても、今後は既知の「ストーリーの共有」をこえて、まさに未知なる「今、起きようとしていること、これから起きるかもしれないこと」についてリアルタイムに多数の知恵を持ち寄って問題解決を図るような、そんな能動的マスコラボレーションの意味をますます持つようになるだろう。
三宅 啓 INITIATIVE INC.

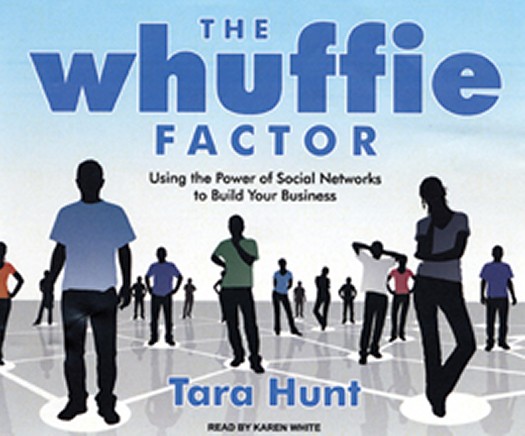

「起きてしまったこと」に対してではなく、「これから起きる可能性のあること」に対しどう対処するかを問うツールとして、一層ソーシャルメディアが活躍するような気がする」
という一節にはっとしました。と同時に、ヘアスタイルや、どんな鞄を選んだらいいか、といった問題と違い、あまりにも「重い選択」が多く、寄せられた情報を取捨選択し、冷静に判断できる基礎をもった人でないとなかなか、難しいのではないかという気もします。
しかし、そこに、tobyoのような静止(ストック型)のアーカイブが合わさってくると違う展開もあるのかなとも考えました。
下山さん
コメントありがとうございます。
「あまりにも「重い選択」が多く、寄せられた情報を取捨選択し、冷静に判断できる基礎をもった人でないとなかなか、難しいのではないかという気もします」
医療に関してはおっしゃるとおりです。それでも今後の医療は、患者自らが選択していく方向へ進むと思われます。その際、選択に伴なう困難をどうサポートするかという点が、関連サービス開発の肝になるでしょう。TOBYOもその一翼を担いたいと考えています。