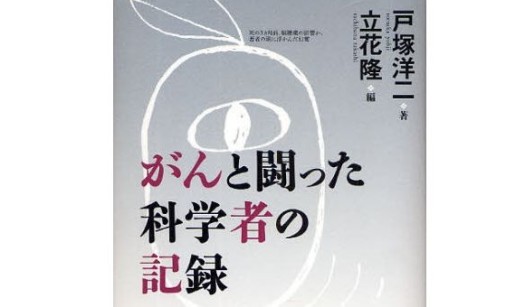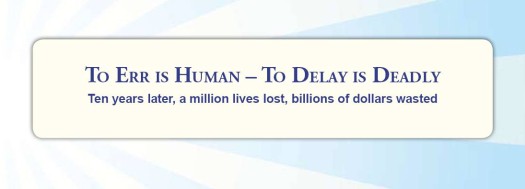昨日エントリでご紹介した「医療情報の権利」宣言は、今後、私たちがインターネットと医療を考える際の重要な基本指針となるだろう。またHealth2.0ムーブメントが、このような宣言を生み出すところまで来たことを素直に喜びたい。一昨年から始まった、インターネットと医療をめぐる世界的な新たな動き。PHR、問題解決型患者コミュニティ、消費者参加型医療、医療情報の流動性の確保、シェアする権利、・・・・などなど。これまでは、ばらばらに存在しているように見えたこれらすべてを「宣言」が繋ぎ合わせ、めざすべき「近未来医療」の方向性を提示してくれたような気がする。
アダム・ボスワース氏のエントリ「Declaration of Health Data Rights」は是非お読みいただきたい。非常にわかりやすく「宣言」の背景と必要性がまとめられている。これを読みながら、「このような発想は、絶対に医療界内部から出てこないだろうな」という感想を持った。だがこの考察は、よく考えてみると何も目新しいものではない。フツウの患者や消費者なら、誰でも日常的に思っていることや感じていることを、ただまとめて述べたに過ぎない。 続きを読む