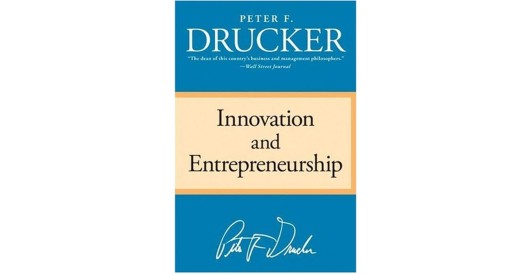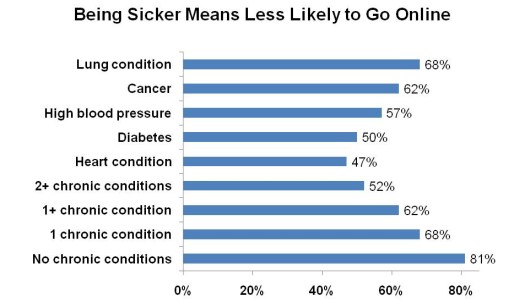4月とは思えない寒い日が続いたが、今日は明るい日差しがたっぷりの爽やかな一日だった。今月は痛風のためほとんど断酒状態で過ごしたが、晩酌をやめると読書にたっぷり時間が取れるのがいい。このまま酒を断つのも悪くないと考えるようになった。
発想が煮詰まりプロジェクト進行が停滞したときは、とにかくまったく関連性のない分野の本を読むにかぎる。別に「何かヒントを掴んでやろう」などと考えずに、ただひたすら思考を別の方面へ向け、そして存分に楽しむことだ。そうすれば、また新鮮な興味を持って仕事を始められる。
TOBYOプロジェクトは今年に入って急速に前進したと思う。収録サイト件数が2万件まで来たこともあるが、いろいろな意味でプロジェクト全体の方向性が視界良好になった。何よりもDFCというキイワードによって、B2Bビジネスが明確になったことが大きい。これによってプロジェクトの事業ドメインがはっきりし、投入する商品を特定することができるようになったわけだ。 続きを読む