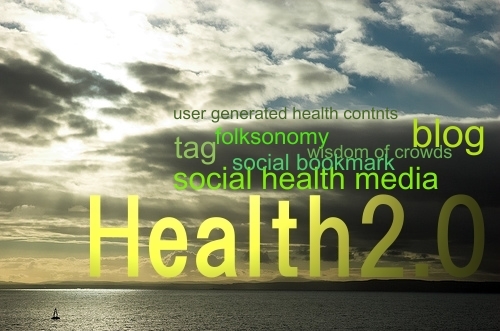先日、Health2.0 Tobyo Chapterでお目にかかったNTTデータシステム科学研究所の石榑康雄さんから、石槫さんが訳出された「パーソナルヘルスレコード—21世紀の医療に欠けている重要なこと」(Holly Dara Miller他著、石榑康雄訳、篠原出版新社)をいただいた。この場を借りて献本御礼申し上げます。
目次
序文
第一章:米国医療の危機的問題解消に求められるePHR
第二章:PHRの歴史と背景
第三章:ePHR、PBHR、EMR、EHRの定義・モデル・機能
第四章:市場要因の進化が後押しするePHR需要
第五章:医師と患者とPHR
第六章:PHRアーキテクチャ
第七章:医療参加者ベースのPHRの計画と実装;実践における検討項目
第八章:PHRにかかわる法規制
第九章:PHRビジネスの持続可能モデル
第十章:おわりに
まずは、日本でようやくPHRについてのこのような基本テクストが上梓されたことを喜びたい。これまでPHRに関してまとまった日本語文献は皆無であったが、この本の登場によって体系的かつ網羅的にPHRの基本知識を得ることが可能となった。これから日本でPHRを様々に議論する際、その共通認識としてこの本が利用されることになるだろう。 続きを読む