昨日、メドピア株式会社の石見社長と比木取締役がお見えになり、来る6月4日に開催されるHealth2.0 Tokyo Chapterのお話を伺った。これで日本においても、ようやくHealth2.0ムーブメントが公然と姿を現すことになるわけだ。
昨日もお話したのだが、思い返せば2006年秋から翌年春にかけて、サンフランシスコ周辺でBarCampやHealthCampなど数多くの医療とウェブをテーマにしたアンカンファレンスが開催されていた。当時、私は東京からそれらの動向を関連ブログや共有サイトなどで毎日チェックしていたのだが、それは前年2005年に爆発したweb2.0ムーブメントが、必ず医療にも波及するはずだとの確信めいた思いがあってのことであった。
活発な議論が交わされる中で、それら無秩序な動きは自然発生的にいくつかのグループを形成し始め、やがて「Health2.0」というシンボルワードのもとへと流れ込み、大きなムーブメントが生み出されていくのを興奮しながら見ていたのである。当時の様々な論争については、このブログの初期エントリに記してあるので、興味のある方はお読みいただきたい。
結局、2007年春にマシュー・ホルトが「この秋、第一回Health2.0カンファランスをサンフランシスコで開催する」と発表し、以後、今日に至る流れができたわけだ。あれから三年が経ち、いよいよ日本でもHealth2.0ムーブメントが始まる。そう思うと、非常に感慨深いものがある。この「TOBYO開発ブログ」は、TOBYOプロジェクト開発の理論構築をめざして設けられたのだが、偶然にも米国におけるHealth2.0ムーブメントの胎動期に逢着し、その誕生と発展をリアルタイムに記録紹介することになったのである。
三年前、まだロゴもマークもなかったHealth2.0のイメージを、ビジュアライズしてみようと当方で勝手に作ったのが上図イメージであった。当方なりの当時のHealth2.0への思い入れを、なんとなく感じ取ってもらえれば幸いである。
だが目を日本のウェブ医療サービスの現状に転じてみれば、あえてHealth2.0と呼べるようなサービスは数少ない。実際、片手で数えるほどしかない。これが現実である。かつて10年ほど前には、医療分野で「eヘルス」という言葉を語る人々がいた。NPOなどが立ち上げられ、マスメディアで報じられ関連書籍も出て、そこそこ話題になったのである。しかし、当時も今も「eヘルス」の成功事例などまったく日本に存在しないのである。そして結局、「eヘルス」はさしたる成果も上げることなく、いつのまにか忘却され空しく消え去ったのである。このようなバズワードの習いとして、現実には何の成功事例もないのに、もっともらしく小器用にバズワードを操る学者や評論家だけが、出版や講演で儲け、売名にあずかっただけ、という構図が繰り返されたのである。
Health2.0ムーブメントはこうであってほしくない。たとえこのようなムーブメントの宿命として、いずれフェードアウトすることが必定であるとしても、何らかの目に見える具体的成果を上げなければならない。なぜなら、それが「医療」という社会インフラにかかわるものだからだ。Health2.0は、かつての「eヘルス」であってはならないのだ。
では「eヘルス」の轍を踏まぬためには何が必要か。まず、あくまで事業プイレイヤー中心で権威主義とは無縁のオープンな風通しの良さだと思う。かつて「eヘルス」では常連であった学者先生や、お役人や、ITゼネコンは要らない。実際にアイデアを持って挑戦し、自分でリスクを取る覚悟のあるプレイヤーこそが、このムーブメントの中心であるべきだ。そして「User Generated Healthcare」というスローガンにあるように、消費者、患者の参加である。参加型医療という新しい医療観が必要なのだ。
三宅 啓 INITIATIVE INC.

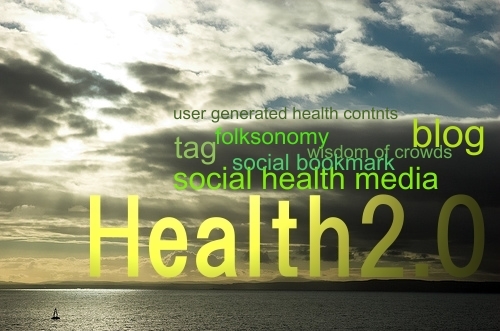

ピンバック: 医師兼社長のブログ» ブログアーカイブ » Health 2.0 Tokyo Chapterのご案内