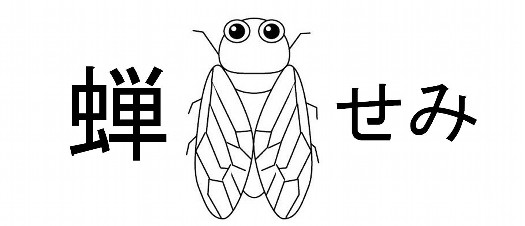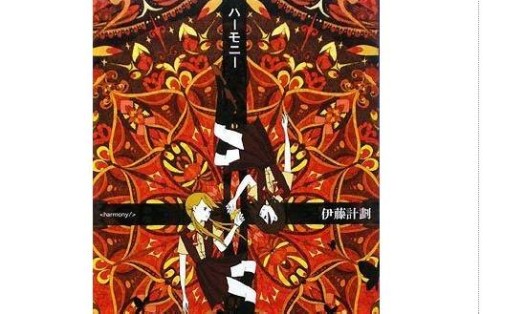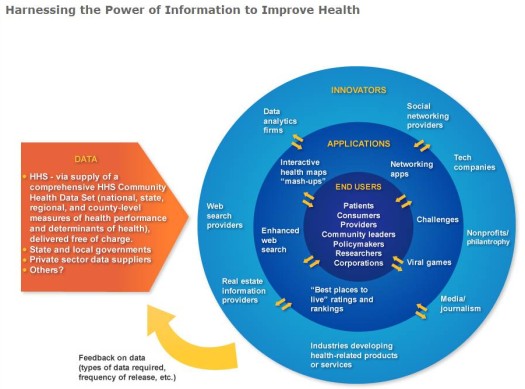「手作りパン」ブームらしい。そう言えば一般サイトのみならず、最近闘病サイトでも手作りパンの話題が多いのに気づく。自分で作ったおいしそうなパンの写真とレシピをアップする闘病サイトが増えているのだ。癌の患者であっても、難病の患者であっても、手作りパンを焼き、その自慢のパンの写真をブログにアップしている。誰かに見てもらうために。「どう?おいしそうでしょ!」。
とりたてて「闘病記」などというと、私たちは何か特別で鹿爪らしい、しかもどこか劇的で非日常的な展開のある「物語」を連想してしまいがちだ。だが、実際は闘病生活においても日常的な時間は淡々と流れている。そこにも手作りパンを焼くような趣味や娯楽の愉しみがあり、家族や友人との会話があり、要するに日常のフツウの生活と時間があるのだ。闘病生活を「闘病記」などという独特の視点で「物語」化したい人たちは、むしろそれら日常の視点が自らに欠落していることを知るべきだ。闘病生活は「戦時」ばかりではない。その多くは「平時」の時間なのだ。
これまで「従来の闘病記と闘病サイトとは質的に違う」ということを再三言ってきたわけだが、その違いの一つは、闘病サイトが闘病生活だけでなく日常生活全体を生き生きと描き出している点にある。もちろん闘病体験だけを焦点化したサイトも少なくないが、多くのサイトは趣味、旅行、娯楽、育児、教育など生活全体を描き出し、その中の一部として闘病体験が記録されている。これに対し、たいていの「闘病記」は紙幅制限のためもあってか、そのような生活全体の記録という体裁を取ることは稀であり、非日常的で劇的な「物語」の骨格を際だたせるような編集がされている。そしてそのことはスーザン・ソンタグが「隠喩としての病」で批判したように、病気を特別視し、過度に文学化(物語化、神話化)するような不健康な表象に繋がっていくのである。 続きを読む