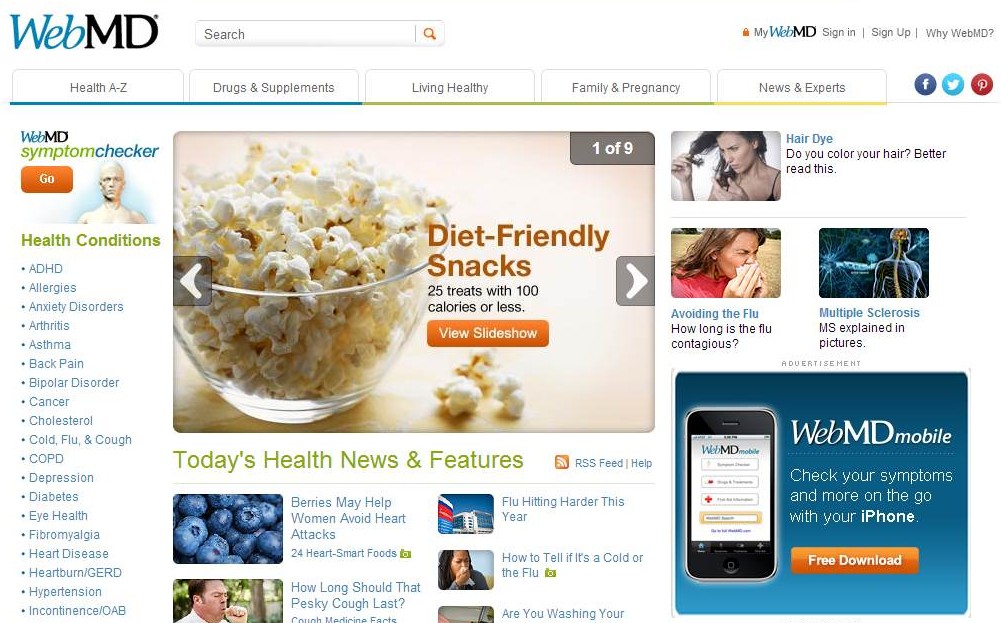このところ厳しい寒さが続いていたが、今日は春を思わせる暖かい一日であった。新宿御苑の梅も開花し始めた。明日から三月である。
患者コーパス
昨日、TOBYO収録サイト数は4万件に到達した。TOBYOは闘病ユニバースの成長と歩調を合わせて成長してきている。貴重な体験ドキュメントを公開してくれた、すべての闘病者の方々に感謝の気持ちでいっぱいである。このように多数の闘病体験が、まとまったドキュメントとして公開されているのはおそらく日本語ウェブ圏だけだろう。
TOBYOは4万サイト、500万ページの闘病ドキュメント・データベースであるが、前回エントリでも述べたように、今後は蓄積された大量のデータからいかに「患者の声にもとづく医療評価」を切り出すかが新たなテーマとなってくる。そのための新たなミッションを「患者言語研究」と呼んでみた。もちろん、従来から私たちがテーマとしていた「患者が体験した事実の可視化」は引き続き追求しなければならないが、患者が医療を語る場合に、どのような言葉を使用しているかを広くリサーチしなければならないと考えている。つまりTOBYOは闘病体験ドキュメント・データベースであると同時に、「患者コーパス」という側面も併せ持っていることを、最近、強く意識し始めている。(注:コーパス(corpus):Wikipedia) 続きを読む