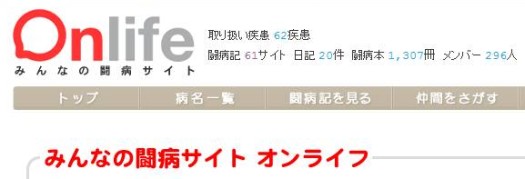昨日エントリで、闘病ドキュメントに対する当方の見方の変化について書いたわけだが、結局のところ闘病ドキュメント自体に関与していかなければ、TOBYOが「体験事実とデータ価値」に向けてその利用方法を進化させていくことはないと思う。現在の闘病ドキュメントはネット上に分散して存在している。当然、分散した情報を分散したまま利用するのがネット的なありかたなのだが、そうはいっても検査データの記録方法などは統一しておかないと、多くの闘病者の体験事例を数値データで集約し統計分析することはできない。つまり本当の意味での「データベース」としての使い方ができないわけだ。
現状は、たくさんの闘病者がネットで情報を公開していながら、それらサイトに蓄積されたデータを集計したり相互比較したりすることもできない。せっかく有用なデータがあるのに、それらを効率的に利用する方法が開発されていないのである。物理学者の戸塚洋二さんなども、実はその点を指摘していたわけだが、これを解決するためにはPHRと合体したような闘病サイトサービスを開発し、そこでデータを記録しながら闘病ドキュメントを書いてもらうしかないと思う。このような闘病サイトサービスにはさまざまなアプローチ方法があるだろうが、PatientsLikeMeなどはSNSというアプローチを選択しているわけである。 続きを読む