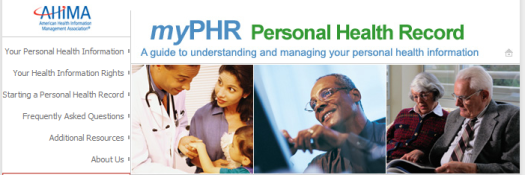PHRの啓蒙に取り組むAHIMA(アメリカ医療情報協会)は、PHRの社会的認知促進のための全米キャンペーンを開始する。すでにAHIMAは無料PHRサイト「MyPHR」を設置し、基本から平易にPHRの機能や利用価値が習得でき、実際にPHRを試してみる環境を提供している。
「このキャンペーンは、アメリカにおける患者中心医療と、実際に個人医療情報にアクセスし利用することを学ぶために、われわれのうち多数が前進していく必要があることを伝えるものだ」。(AHIMAのCEOリンダ・クロス氏,Digital Healthcare & Productivity.com,Oct 16,2007) 続きを読む