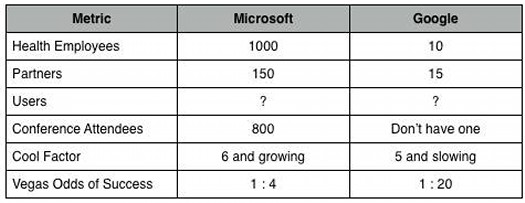今月、米国ミシシッピー州は、ウェブベースのEHR(Electric Health Records)を無料で医師に提供すると発表した。このEHRの目的は、ミシシッピー州在住60万人のメディケイド(低所得者向け公的医療保険)加入者へのサービス向上にあり、加入者の検査データ、投薬、予防接種、アレルギー等についてのデータを集約している。さらに電子処方箋、退院情報へのアクセス、ケアの空隙を特定するための支援ツールなどアプリケーションも提供する。このEHRは基本的にはメディケイドが持っている医療データを集約し、医療現場に無料で提供するものであるが、メディケイド以外の関係機関が保有するデータも集める必要があり、そのためにHIE(health information exchange)ソフトウェアをShared Health社から調達している。
このケースを読んでいろいろ考えさせられたのだが、一言で言うと、これは「ペイヤー(保険者)サイドのEHR」である。従来、EHRと言えば「医療機関のEMRを広域で集約したもの」というふうに、あくまでも医療機関を起点として考えられてきた。だが、個人の医療情報は保険者側の手元にも大量に集まっており、これをDB化すればたちどころに医療機関を横断するEHRになるわけである。そしてこれをウェブベースで運用すれば、医療機関の枠にとらわれずに、患者個人の医療情報をいつでも一か所に集約できるわけだ。なおかつ、医療機関側ではシステム設置コストも運用コストもかからない。ただ医療機関側のEMRとのスムースな情報交換だけが問題になるが、これもHIEを使用すれば解決するわけだ。つまりこのミシシッピー州のケースは、EHRなど医療情報システムのありかたについて、医療機関以外の多様なプレイヤーの多様なイニシアティブによっても、多様に成立することを示している。