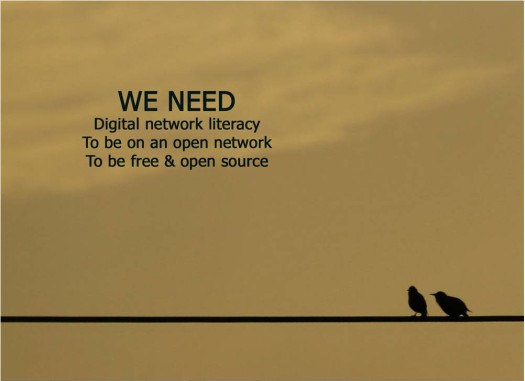DFC(Direct from Consumer)開発に取り組む過程で、TOBYOプロジェクトの役割というものをあらためて考え直す機会を持つことが出来たのは幸いだった。これまでプロジェクトミッションは「ネット上に存在するすべての闘病体験を可視化する」と定義してきたのだが、さらにもっと直截で具体的な表現を用いるとすれば「医療事実の蒸留器(distiller)」とでも呼べるかも知れない。
まずTOBYOは、ネット上に多数存在するスパムサイトや偽装サイトなどのノイズを除去し、自発的に公開された闘病記録を含むサイトだけを収集してきている。つまりGoogleやYahooのような汎用検索エンジンに比べると、よりクリーンな情報ソースだけを検索することが可能だ。これはバーティカル検索の強みである。
だが一口に「闘病体験を含むサイト」と言っても、闘病記録がほぼ100%を占めるようなサイトからわずか10%程度のサイトまで雑多なバリエーションがある。私たちが2万件を越えるサイトを見てわかったのは、むしろ闘病記録よりも日常雑記の方が全体として情報量は多いということだ。育児、教育、仕事、趣味、旅行、時事など、多彩な日常記録が公開されており、その中の一部分として闘病記録が収載されているのが普通である。 続きを読む