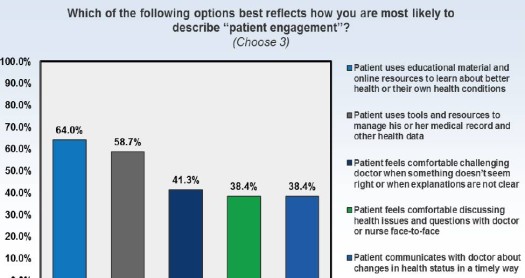この連休もようやく昨日から5月らしい晴天になった。ところで当方、あいにく体調が悪く、自宅蟄居状態の日々を過ごしていた。どこへ出歩くということもなかったが、雨模様の合間に、妻と新宿へ映画「裏切りのサーカス」を見に行った。この映画は良かった。淡々とシーンを重ね上げる寡黙な作りの映像に好感を持った。ストーリーよりも絵(映像)が良いので、ただじっと見とれていた。あとは自宅で音楽を聞き、本を読み、部屋の片づけをやり、石神井公園を散歩し、あれこれ事業の今後を考えるうちに連休は終わった。
そのあいだも社会は動いている。厚労省は癌患者情報の医療機関による報告義務づけ構想を発表した(日経5月2日「がん情報 全国一元化 病院に登録義務、厚労省検討 」)。
国が集めたがん情報は当面、国立がん研究センターが一元管理する。患者数や生存率の統計はホームページなどを通じて一般市民でも入手できるようになる。将来的にはがんになった際、自分に適した治療法や医療機関を調べる情報源とすることを厚労省は検討している。患者や病院は国や都道府県を通じて情報を提供してもらう。例えば、データベースを通じて症状ごとに治療経験が豊富な病院がいち早く分かれば、患者の早期治療につながる効果が期待できる。
とのことであるが、これまで正確な癌患者数など基礎データ把握さえおこなわれていなかったとは・・・驚かざるを得ない。遅まきながらもデータを収集し公開することに異存はないが、データ公開の方法は「国立がん研究センター」など政府系サイトを通じてではなく、ぜひ海外の「オープンガバメント」のやりかたを研究してもらいたい。すなわち政府系サイトを作るのではなく、データを一般に公開する方法を採用すべきだ。 続きを読む