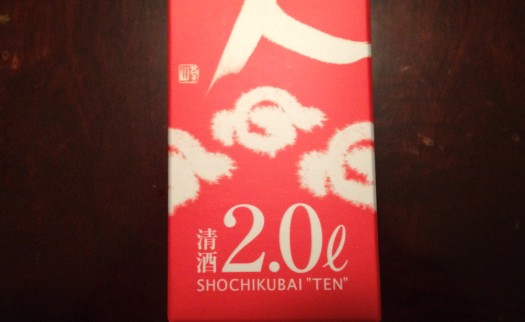Announcing Medicine X 2012 from Larry Chu on Vimeo.
前エントリでも少し触れたように、ここのところ徐々に「Health2.0」という言葉は、単に特定のイベント興行ブランド・ネームへと格下げされたかのような感が強い。なぜ「格下げ」が起きたかというと、Health2.0以外に多数の医療ITカンファレンスが続々と実施され、さまざまなムーブメントも立ち上がってきているからだ。その中でも、若者中心のスタートアップ企業が大挙結集して注目を集めたのがRock Health主催の“Health Innovation Sumit” で、今年1月サンフランシスコで開催されている。
また、最近注目されているのがこの9月開催される“Stanford Medicine X”。プロモーションビデオ(上)が公開されているが、自分のICD(植え込み型除細動器)データへのアクセスを主張して話題になったe-PatientのHugo Campos氏も参加する予定。
ちなみに、夏までに開催が予定されている主な医療ITカンファレンスは下記の通り。
●Healthcare Experience Design Conference
●Innovations & Investments in Healthcare
●Kauffman Life Science Ventures Summit
三宅 啓 INITIATIVE INC.