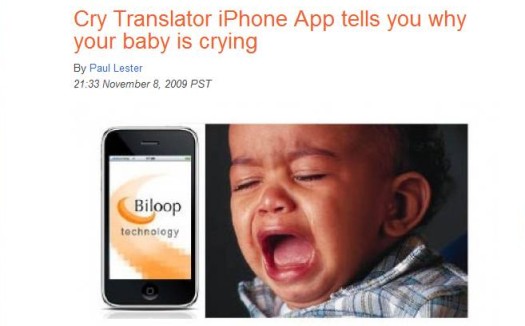先月29日、読売新聞は医療・介護・健康情報サイト「ヨミドクター」を開設した。新聞社の医療情報サイトはこれまで各紙が展開してきているが、この「ヨミドクター」はいくつかユニークな特徴を打ち出している。なかでも「病院の実力」は「病院選びの強い味方」をキャッチフレーズに、アウトカム情報に一歩近づいた医療評価データを提供しており注目される。
先月29日、読売新聞は医療・介護・健康情報サイト「ヨミドクター」を開設した。新聞社の医療情報サイトはこれまで各紙が展開してきているが、この「ヨミドクター」はいくつかユニークな特徴を打ち出している。なかでも「病院の実力」は「病院選びの強い味方」をキャッチフレーズに、アウトカム情報に一歩近づいた医療評価データを提供しており注目される。
全国約3,000病院の独自調査をもとに、病名と地域を選ぶことで、病院ごとの患者数や手術件数、専門スタッフなどが一覧で見られるサービスです。データを自由に並べ替えることができ、地方発の病院情報もネットで初めて提供する目玉コーナーです。(プレスリリース「読売新聞が、頼れる・役に立つ医療サイト「ヨミドクター」をオープン」より)
これは上の画面写真のようなスプレッドシート形式で、病名・疾患ごとに病院の治療状況を一覧比較できるもの。画面写真はおそらく「乳がん」治療の実施状況の画面だろうが、全摘手術から温存療法までの各治療法構成比率を、病院間で比較することができる。これまで、単に手術件数を病院ごとに集計するムックなどはあったが、この「病院の実力」はそこからさらに踏み込んで、詳細な病院ごとの治療状況を提供している。 続きを読む