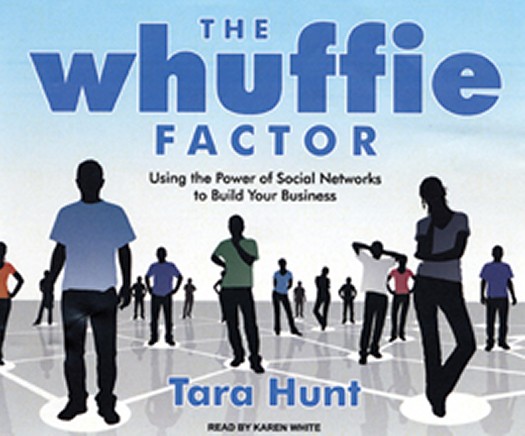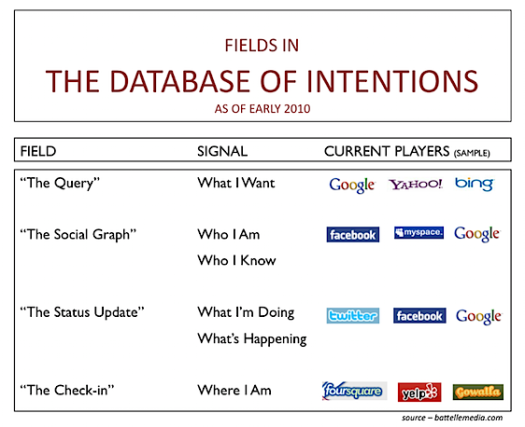アマゾンのキンドルやアップルのiPadの登場によって電子出版が現実化しつつある中で、出版業界は危機感を募らせているようだ。それでも紙の本がそう簡単に姿を消すとも思えないのだが、逆に従来の不透明な流通過程や高コストの印刷・製本パッケージングがこのまま存続できるとも思えない。コンテンツを従来の「本」に閉じこめておくこと自体が、ますます困難になっていくことはまちがいない。
このような時期にちょうどピッタリのビデオが現れた。このビデオはPenguin Publishing Groupの英国出版社であるDorling Kindersle社が社内の営業会議のために制作したものだが、社内の評判があまりにも高かったので公開に踏み切ったらしい。今日の出版業界のきわめて悲観的な状況を語りながらも、同時に出版と書物の価値を積極的に肯定するという離れ業を演じている。このビデオには、21世紀初頭の出版業界が直面する「危機と希望」という「未来の二つの顔」が描かれている。
冒頭”This is the end of publishing and books are dying….”という刺激的な言葉によって、出版業を取り巻く悲観的な状況のナレーションが始まる。だが途中でナレーションは反転し、同じ原稿をリバース読みしていく。そうすると・・・・・。うーん、うまい。拍手!。
三宅 啓 INITIATIVE INC.