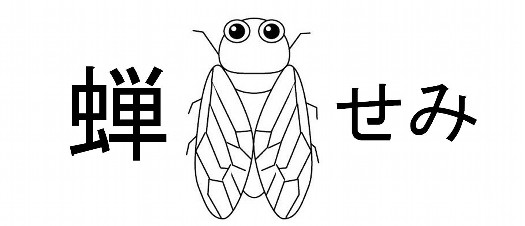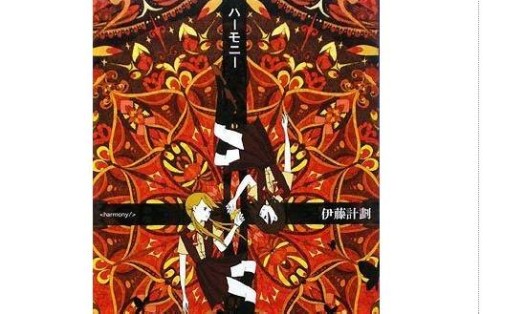梅雨明けはまだか。夏を待つ週末。でも梅雨が開ける前にやることがある。蝉どもが喧しく鳴き始める前に静かに音楽を聞くこと。ここ石神井公園の夏は蝉の声で充満し、スピーカーから出てくる音の高音部が聞き取りにくくなるほどだ。特にドラムスのハイハットの切れがマスクされ、リズムのタイトさが劣化する。蝉が来る前に音楽を聞かねばならないし、その後は蝉が去るまで、秋まで待つしかなくなる。というわけで音楽を聞き込む週末になった。
そして昨日は選挙。今回の参院選はとにかく盛り上がりにかける選挙だった。いつのまにかなんとなく始まり、そして大方の予想通りの結末を確認するだけで終わった。だが、民主党の政治家というのはどうしてこうもやり方が稚拙なのか。長年の野党体質が染み付いてしまったせいか、権力行使の局面でぎこちなくあたふたするだけのように見える。「柄に合わない」ことを無理にやっているように見える。その場逃れの弥縫策しかないのか。今必要なのはビジョンドリブンな政策を提起できる政治家だが・・・・・。
さて、昨日の朝日新聞beを眺めていたら、次のような記事が目に入った。タイトルは「医師の技術や知識を人々に解き放ちたい」というもの。 続きを読む