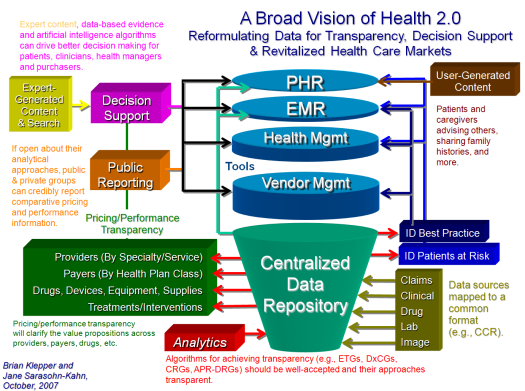10月14日付FinancialTimesによれば、ファイザーが医師SNSのSermoと契約を結んだことが明らかになった。
「ファイザーは、Sermoの医師コミュニティや他のSermoパートナーと協力し、コラボレーションを通じ、以下のような主要目的を追求する計画である。
・動きの速いソーシャルメディア環境において、医師と共に、医療情報交換を変革する最良の方法を発見する
・オンライン交流によって提供されるイノベーティブ・チャンネルを通じて、医師とのオープンで透明性のあるディスカッションを創造する
・医療プロフェッショナルとのコミュニケーションにおけるソーシャルメディア利用のためのガイドラインを、FDA(米国食品医薬品局)と連携して明らかにする
・製薬プロフェッショナルとSermoコミュニティの間の生産的な交流開発を、医師と連携して進める」(“Pfizer takes a leaf out of Facebook”,FT.com,October 14 2007)
上記の提携内容だけでは、いったいファイザーが何を具体的にSermoで目指しているかはっきりしない。ただ、従来、製薬メーカーは医師とのコミュニケーションのために膨大な予算とエネルギーを投じており、これはコストの割には効率が悪いと言われている。そのため、今後、医師とのコミュニケーション活動を合理的にコストダウンし、同時にコミュニケーション効果を改善する手法として医師SNSに着目したとみられている。 続きを読む