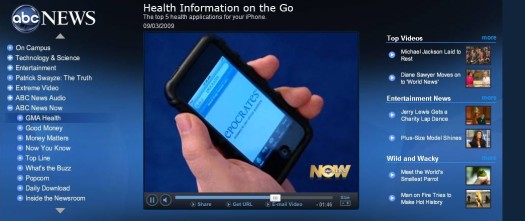医療情報はウェブ上に氾濫しているが、本当に自分にとって必要な情報が見つからない。依然としてこのような消費者、闘病者にとっての「現実」が存在しており、これをどう解決するかが、ウェブ医療情報サービスに問われているのである。そして皮肉なことに、最も入手が難しいのが自分の健康状態に関する医療情報である。自分に関する医療情報は医療機関のEMRやEHRに蓄積されているはずだが、その情報に消費者・闘病者が直接自由にアクセスすることはできない。「自分に関する情報」であるのに、それにアクセスすることさえできないという、きわめて理不尽な状況がある。
たしかにEMRやEHRは医療者側の業務システムであり、消費者・闘病者がアクセスすることは想定されていない。だがこれでは消費者・闘病者側が自分の健康に関心を持ち、あるいは主体的に自己の疾患と向き合うことはできない。そこでPHRが必要になってくる。
先週、日経夕刊で政府の「電子私書箱」構想の記事を目にした。ここ二-三年の間に、たびたび目にしてきた「電子私書箱」だが、記事にはPHRに近い機能が盛り込まれているように書かれていた。また昨年来、経産省が中心になって「日本版PHR」の研究会や実証実験が進められていることも承知しているが、正直のところ、これら官庁主導プロジェクトを積極的にトラッキングしようという意欲も関心も薄れるばかりだ。久しぶりに「電子私書箱」や「健康情報活用基盤構築のための標準化及び実証事業」などの動向を少し調べてみたが、「電子私書箱」については、6月30日に発表されたグランドデザイン「i-Japan 戦略2015」における「各論」という位置づけになっていることがわかった。 続きを読む →
 この夏、日本初の闘病記専門検索エンジン「TOBYO事典」の改良に取り組んできたが、新たに開発したクローラをいよいよ今月中には運用する予定。5月から、1万件の闘病サイトを対象に200万ページの検索インデックスを作成しテスト運用を開始してきたが、今回の改良版では、対象1万5千サイト、検索インデックス300万ページへボリュームアップし、なおかつ検索精度の向上を目指している。
この夏、日本初の闘病記専門検索エンジン「TOBYO事典」の改良に取り組んできたが、新たに開発したクローラをいよいよ今月中には運用する予定。5月から、1万件の闘病サイトを対象に200万ページの検索インデックスを作成しテスト運用を開始してきたが、今回の改良版では、対象1万5千サイト、検索インデックス300万ページへボリュームアップし、なおかつ検索精度の向上を目指している。