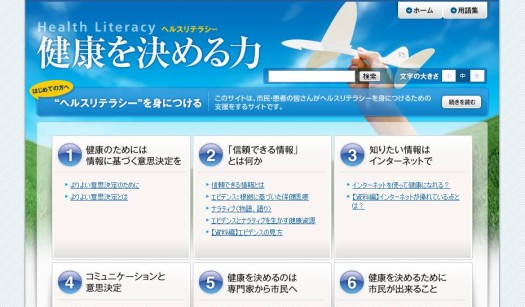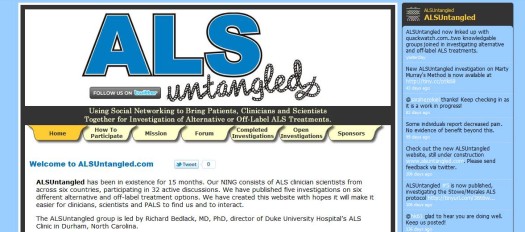「日本のHealth2.0」というイシューが語られるようになったのは、今年の夏、六本木ヒルズで開催されたHealth2.0 Tokyo Chapter2からだと思う。当日、私もパネルディスカッションに参加し意見を述べたが、現状を見れば事業プレイヤーの数の少なさは覆うべくもない。
私たちのTOBYOは、米国におけるHealth2.0ムーブメントに大きな刺激を受けてきた。2006年以来、米国のHealth2.0シーンはウェブ医療サービスの実験場であり、ありとあらゆるビジネスモデルが登場しては消えていった。一説では2,000社のスタートアップ企業がローンチしたとも言われている。その中で成功したとされる企業は数少ないが、とにかく膨大な量のチャレンジがこの分野に集中したのだ。成功したケースに学ぶことは必要だが、多くの失敗ケースもまた貴重な教訓をあとに続くものに語ってくれている。
その中で徐々に、「このケースはうまくいくが、このケースが成立する余地は少ない」というふうに、いくらか見通しが立てられるような状況が生まれている。だが、米国と日本では医療制度がかなり異なり、事業のフィージビリティを同一視できるわけでもない。米国における実験に学びながら、日本固有の状況に適応していく必要もある。
「日本のHealth2.0」というイシューがいくばくかの有効性を持つためには、まず何をおいてもプレイヤーの量が増えることが大前提となるだろう。20代、30代の若いファウンダーがこの分野でどんどん出現してくるような状況が必要なのだ。それがイメージできないのなら、このイシューはなんの現実的な基盤も持たず、単なる同好の士の趣味談義と変わるところはない。 続きを読む