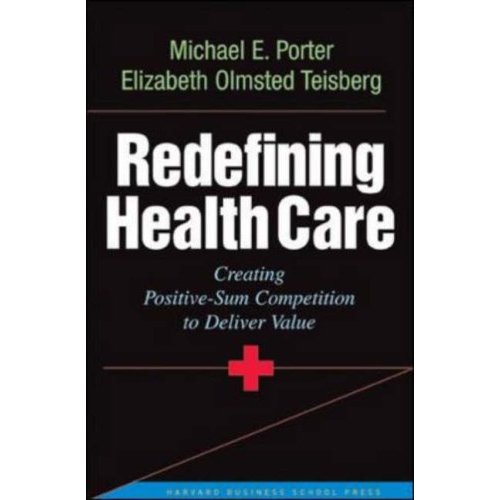Impress Watch「BB Watch」の連載コラム「下柳泰三の今週のヨカッタ!!」で、TOBYOが紹介された。ツールとしてのTOBYOのツボを、非常に要領よく押さえた記事を書いてもらったと感謝している。どうもありがとうございました。
以前からこのブログで書いてきてはいるが、この記事を読みながら、改めて「闘病ネットワーク圏のツール」というTOBYOの立ち位置を再確認させられた。つまり、「ネット全体に広がる一つの闘病コミュニティ」というものが既に日本語ネット圏には存在しており、それを効率よく、便利に、みんなが使うためのツールとしてTOBYOがある、ということである。
われわれは、「ネット上の闘病記」つまり闘病サイトと、それらによって形成されるミクロコスモスである「闘病ネットワーク圏」の豊かな可能性にこだわっている。その可能性は、決してリアルの「闘病記」やリアルの「患者会」に代替されたり、還元されたりするようなものではない。それらの可能性は、代替不能な独自性として理解すべきものなのだ。
話はとぶが、米国Facebookは「NetOS」をめざし「最大のプラットフォーム」をめざしているらしい。だがそれは、結局、実現不可能だろう。なぜなら、われわれの眼の前には「インターネット」という「唯一にして最大のプラットフォーム」がすでに存在するからだ。それと同じように、日本のわれわれの目の前には、「唯一にして最大の闘病者コミュニティ」としての「闘病ネットワーク圏」が既に存在している。
三宅 啓 INITIATIVE INC.