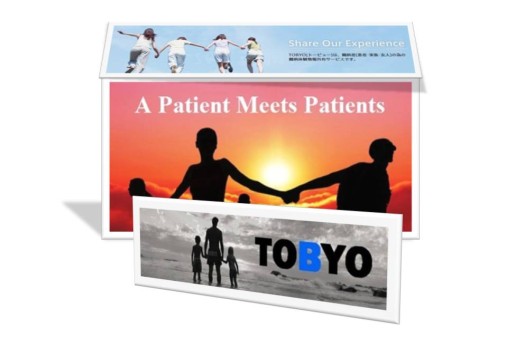「破壊的イノベーション」(Disruptive Innovation)とは、ハーバードビジネススクールのクレイトン・クリステンセン教授が「イノベーションのジレンマ―技術革新が巨大企業を滅ぼすとき」(Harvard business school press)で展開した経営コンセプトであるが、先月、今度はこのコンセプトを医療に適用した新著「THE INNOVATOR’S PRESCRIPTION: A Disruptive Solution for Health Care」が発表された。
クリステンセンのこの新著は、早速、New York Timesが「Disruptive Innovation, Applied to Health Care」(1月31日)で取り上げている。またHealth2.0コミュニティでも注目を集めており、中心的論客スコット・シュリーブ氏は、自身のブログでクリステンセンの共著者Jason Hwang氏にインタビューを試みている。 続きを読む