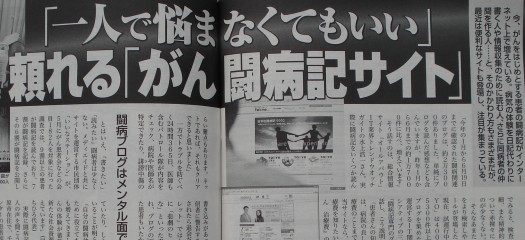梅雨の中休みが続いているが、もう気分は夏へ向かっている。TOBYOはベータ版を公開したが、バーティカル検索「TOBYO事典」の検索対象拡大など、やらなけらばならない仕事は山積している。TOBYO事典のテスト運用をしてみると、当初予定していた以上のインデクシング・ページ数が発生していることがわかり、リソース調整など新たな課題も出てきている。全病名の横断検索実現のためには、今少し時間がかかるかもしれない。 続きを読む
カテゴリーアーカイブ: 闘病記
サンデー毎日(7/13号)にTOBYO紹介記事
本日発売のサンデー毎日(7/13号)に掲載された記事「『一人で悩まなくてもいい』頼れる『がん闘病記サイト』」でTOBYOを紹介してもらいました。ありがとうございました。
これまで闘病記といえば、出版されたリアル闘病記の方に目が行きがちで、闘病サイトの方はどちらかと言えば胡乱な目にさらされてきた感があります。その意味では、このサンデー毎日の記事は、春先の西日本新聞記事とともに、マスコミが闘病サイトを正当に評価した記事として価値があると思いました。
これまで過小評価の憂き目にあってきた闘病サイトですが、この記事をきっかけとして、さらに社会的な注目が集まればと思います。もちろん、これら闘病者によって制作されたコンテンツは玉石混淆ですが、これらの中から優れたコンテンツを選び出していく役割も、今後TOBYOは果たしていきたいと考えています。
三宅 啓 INITIATIVE INC.
闘病記は「患者-医師」関係を毀損するか?
最近、多数の方々とお目にかかり、当方のTOBYOやHealth2.0や闘病サイトについて訊ねられたり、あるいは意見交換したりする機会が増えてきている。TOBYOは先月ベータ版を公開したが、まだバーティカル検索「TOBYO事典」が限定公開の状態であり、こちらから一切正式の告知活動はしていない。にもかかわらず、多くの方々に関心をもっていただいて訪問を頂戴していることはありがたいことはもちろんだが、正直のところ、当方にとっては予想外の展開でもある。
さて、それら意見交換の中、特に闘病サイトに関して最近よく異口同音に質問されるのは、「闘病サイトによって、患者と医療者の関係が悪化する危険性」という問題に関してである。当方は、当然、闘病サイトの役割をこのブログで積極的に評価して来ているが、このような「問題」を指摘する視点もまた存在するのかと、少々面食らいつつ、その意外感は大きい。 続きを読む
「BB Watch」でTOBYOを紹介
Impress Watch「BB Watch」の連載コラム「下柳泰三の今週のヨカッタ!!」で、TOBYOが紹介された。ツールとしてのTOBYOのツボを、非常に要領よく押さえた記事を書いてもらったと感謝している。どうもありがとうございました。
以前からこのブログで書いてきてはいるが、この記事を読みながら、改めて「闘病ネットワーク圏のツール」というTOBYOの立ち位置を再確認させられた。つまり、「ネット全体に広がる一つの闘病コミュニティ」というものが既に日本語ネット圏には存在しており、それを効率よく、便利に、みんなが使うためのツールとしてTOBYOがある、ということである。
われわれは、「ネット上の闘病記」つまり闘病サイトと、それらによって形成されるミクロコスモスである「闘病ネットワーク圏」の豊かな可能性にこだわっている。その可能性は、決してリアルの「闘病記」やリアルの「患者会」に代替されたり、還元されたりするようなものではない。それらの可能性は、代替不能な独自性として理解すべきものなのだ。
話はとぶが、米国Facebookは「NetOS」をめざし「最大のプラットフォーム」をめざしているらしい。だがそれは、結局、実現不可能だろう。なぜなら、われわれの眼の前には「インターネット」という「唯一にして最大のプラットフォーム」がすでに存在するからだ。それと同じように、日本のわれわれの目の前には、「唯一にして最大の闘病者コミュニティ」としての「闘病ネットワーク圏」が既に存在している。
三宅 啓 INITIATIVE INC.
Twitterと医療
 | View | Upload your own
| View | Upload your own
2月ごろのエントリ「twitterで禁煙!: qwitter」 以来、実は「twitterって、医療と親和性あるんじゃないかなぁ」とずっと考えて来た。先のエントリでも医療への応用可能性をいくつか指摘してみたが、その後、まだ日本ではこの分野へのチャレンジはなさそうだ。TOBYOとの関連で言うと、たとえば闘病生活のデータ記録ツールとしてtwitterの可能性を追求してみる値打ちはあるかもしれない。
などと考えているところへ、まさに「Twitter for Health」というタイトルのプレゼン・スライドを偶然見つけた。これを見ると、米国では徐々にtwitterベースの医療・健康情報サービスが増えてきているのがわかる。ざっと見ているだけでも、いくつかヒントがつかめるはずだ。誰か一緒に開発しませんか。
三宅 啓 INITIATIVE INC.