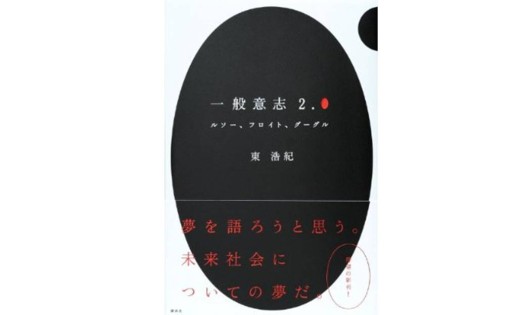先週は嵐。今週は花吹雪。花も嵐も踏み越えて行くが男の生きる道。いささか古いか・・。
ひたすら闘病ユニバースの可視化とデータ収集に励んできた4年間だったが、dimensions、CHART、TDRと開発は進んできた。最近、もう一度私たちが目指してきたことをあらためて確認しなおす必要があるような気がしている。今の時点で、私たちが目指してきたことを短く言えば、それは「患者ドキュメントによる医療評価」ということではないかと思う。これを実現するためには、とにかく患者ドキュメントを大量に集めなければならなかった。そしてデータ量が確保されたら、次にそれを使って「評価」というものを生成しなければならない。これは「データを評価へ変換すること」とも言える。
dimensionsはその変換のための基本ツールであったが、それはまだ「評価」自体を提示するものではなかった。ユーザーの多様な目的に即して自由にデータを抽出するツールであり、特定の「評価」を出力するためのものではなかった。開発当初は、このような多目的ツールであることがユーザーのニーズに合致するものだと想定していた。
そして先月から本格的に取り組んでいる「がん闘病CHART」では、だんだん「評価」へ踏み込んだ出力というものをイメージするようになってきている。それはユーザーの自由度にある種の制限を設けて、一定のフレームでデータを見ることによって実現されるものだ。データの解釈が全面的にユーザーに任されているような状況では、「評価」はユーザー自身の手に委ねられている。たとえばマーケティングや製品開発などプロフェッショナルな仕事をしている人達であれば、本来なら医薬品や治療法など、ある事象に対する「評価」はツールを使ってデータを検討しながら自分自身で行うべきだろう。またそのような技量と経験を持つがゆえに「プロ」であるとも言える。 続きを読む