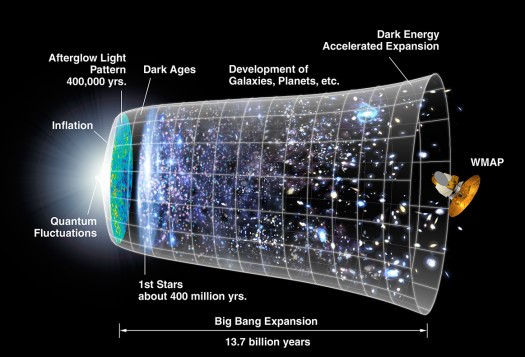いささか夏ばて気味。世間はリゾート気分一色。ブログ更新も滞りがち。夏なんです。
週末、ヘミングウェイ「移動祝祭日」(高見浩訳、新潮文庫)、「愛と憎しみの新宿」(平井玄、ちくま新書)を読む。「移動祝祭日」はヘミングウェイの実質上の遺作であるが予想外の収穫だった。1920年代のパリ。文学、都市生活、レストラン、カフェ、酒、競馬、釣り、そして様々な人間模様。簡潔な筆致。深く鋭い洞察。書くことは生きることであるように、読むことは生きることである。そのことを堪能できる作品である。「愛と憎しみの新宿」は、新宿の「あの時代」の記憶を呼び起こすものだ。だが読み進む内に、これらどこにも焦点を結ばない記憶の羅列に苛立ちを感じはじめた。そして先週読んだクリステヴァの次の一節を思い起こした。
ニーチェはすでに、「つねに重くなってゆく過去の重さによりかかった」「人間動物」を告発していた。この人間動物---すべてを忘れるがゆえに苦しむことのない動物の正反対のものとして---は、逆に「忘却を学ぶことができず、つねに過去のとらわれ人となっていること」で苦しみ疲れ果てている。恨みと復讐の念を増大させる記憶の反芻に対して、ニーチェはまさに「忘却力」を、「抑制力、とくにポジティブな能力」を強く推す。(「ハンナ・アーレント」ジュリア・クリステヴァ、作品社、第三章-5「判断」P305)
この言葉は、何かを思い出し記憶を再現することよりも、「忘却するチカラ」の方が重要であると教えてくれている。「新しいものに場所をゆずるために、私たちの意識を白紙状態(タブラ・ラサ)にする」。確かに何か新しいことを始めるためには、まず以前の記憶を積極的に忘れ去ることが必要なのだ。 続きを読む