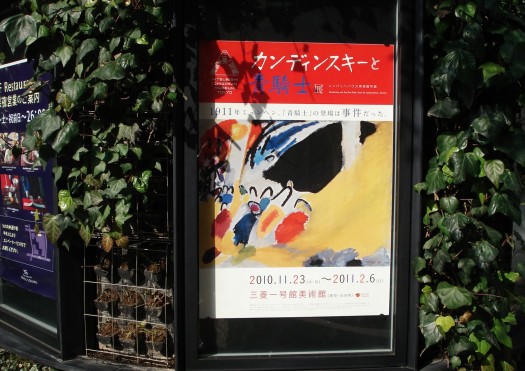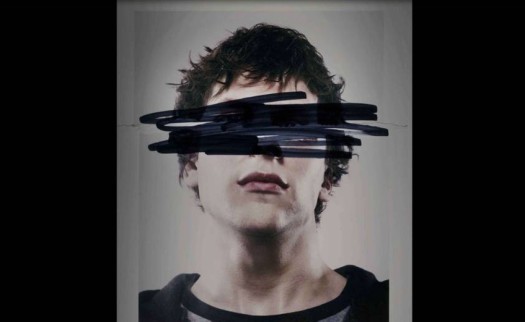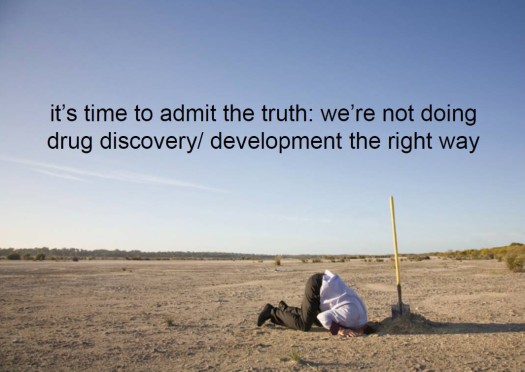昨日、2月18日。TOBYOはサイトオープン3周年を迎えた。夕方、早々に仕事を切り上げ、事務所から明治通りを歩いて東新宿方面へ向かい、新大久保はずれの韓国家庭料理屋へ。午後から急に風が冷たくなったが、暖かいカムジャタン(写真)をつつき、薬缶に入ったマッコリを飲みながら、奥山とこの三年を語り合った。
収録サイト2,000でスタートしたTOBYOは、三年経って収録2万6千サイトと文字通り国内最大の闘病サイトライブラリーに成長した。当初なかった闘病サイトだけを対象とするバーティカル検索エンジンも稼働している。そして昨年から開発に着手したdimensionsも、基本開発段階を終えデビューを待っている。振り返ってみれば、三年という時間がどうしても必要だったと思う。
Health2.0関連のビジネスモデルがweb2.0一般のそれとはかなり異なることは、再三、このブログで指摘してきているが、TOBYOの場合、収録サイト数や検索インデックスページ数など量的蓄積のための時間が必要だった。では2万6千サイトで十分かと言えば、まだまだと思う。医療におけるリサーチ・イノベーションを実現する最低水準は2万サイトぐらいだが、もちろんデータは多ければ多いほどよい。三年経ってようやくリサーチ・イノベーションをはじめ、さまざまなチャレンジを実現する基礎が固まったというところだろう。 続きを読む