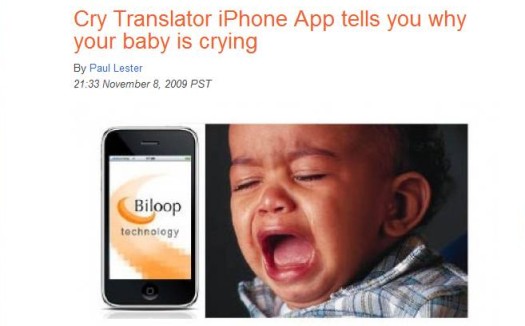闘病体験専門検索エンジン「TOBYO事典」だが、改良版の公開が遅れている。クロールは既に終了しているのだが、データをチェックしてみると当初目標に対して達成度がやや不十分であり、修正と今後の作業方針など検討している。TOBYOプロジェクトのミッションは「ウェブ上のすべての闘病体験を可視化し検索できるようにする」ことであるが、これを最も早く確実に実現するための方策を考えている。
現時点で想定しているのは、複数の検索エンジンをTOBYOに装備することだ。現状のTOBYO事典のような闘病ユニバース全体を見渡す検索エンジンは必要だが、他方、各疾患別に特化した検索エンジンを複数設置する必要があると考えている。たとえば「がん疾患グループ」専門の検索エンジンとか、「メンタル疾患グループ」専門の検索エンジンなどを設置し、闘病者の個別ニーズにより一層特化し、きめ細かい情報検索ができるようにしたい。闘病者の情報ニーズは、闘病一般とか医療情報一般についての情報にではなく、特定疾患の特定症状についての情報を指向している。つまりその情報ニーズは個別化し細分化しているのであり、それに対応した情報提供が求められていると思う。
TOBYOは現時点で805疾患を収録しているが、もちろんこれらすべてに特化した検索エンジンを設置することはない。おそらく、疾患をいくつかの「疾患グループ」にまとめることになるだろう。来春稼働を目指したい。
これらのことを通じて、よりクリーンでニーズにきめ細かく対応した情報検索、あるいはより実践的に闘病に役立つ情報検索を実現し、GoogleやYahooなど汎用検索エンジンとの一層の差別化を図っていきたい。
三宅 啓 INITIATIVE INC.