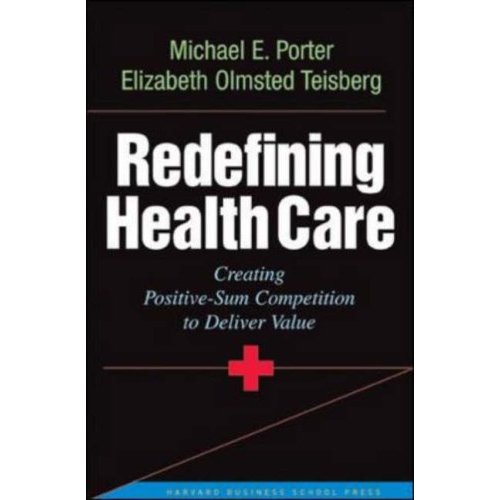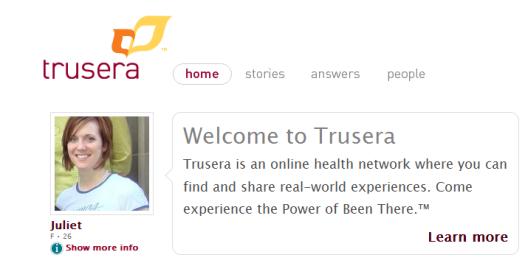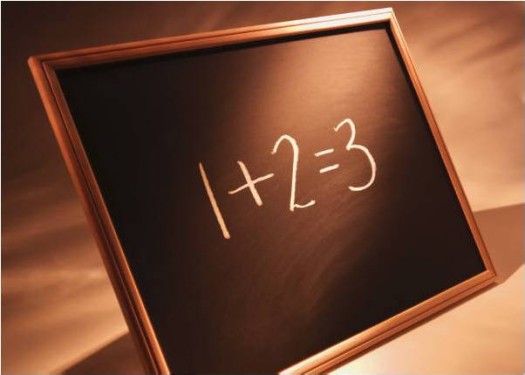昨日(6月22日)、朝日新聞に「医療再生へ—危機感共有 あとは実行」という記事が掲載された。日曜日の朝食を食べながら、一通り記事を眺めたのだが、全体としては何か散漫な印象しか残らなかった。医療関係の識者二名と朝日側の論説からなる三つのパートが、何もほとんど噛み合うこともなく並置されており、結局のところ、どんな意図でこの記事が作られたのか首をひねらざるを得なかった。
その「散漫な印象」の原因は、「医療再生」という共通テーマがありながら、結局それを掘り下げて議論するための共通テーブルが設定されておらず、それは「編集」の側の問題が大きいと言えるだろう。つまりここに登場している三者が、同一テーブルではなく、それぞれ自分専用のテーブルに陣取って顔を見合わせることもなく、てんでに物を言っているような、そんな空々しさを感じたのである。 続きを読む