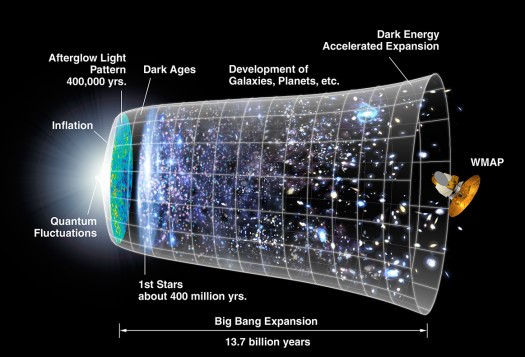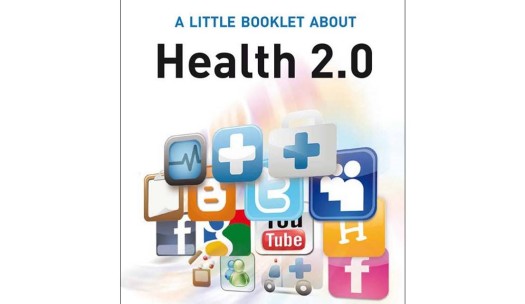昨日、暑い中を妻と「マン・レイ展 ~知られざる創作の秘密~」(国立新美術館)へ出かけた。美術館は朝から大混雑。これはオルセー美術館展を観る人達がほとんどで、館内を埋めつくす長蛇の列には驚いたが、マン・レイ展の方は人も少なくゆっくり鑑賞することができた。
以前から自宅の机の上にマン・レイのポスターを飾っている。マン・レイの妻ジュリエットのモノクロ写真に手描きのラインを書き入れたポスターだが、なんとも言えない味があり気に入っている。展覧会を見終えて何かいまいち物足りなかったのは、このポスターが出展されていなかったせいもあるのか。パリ時代のヘミングウェイと息子バンビの写真があったのも意外だった。同時にマン・レイ作の映画も上映されていたが、かつて京都のシュールリアリズム映画祭で見た記憶があり懐かしかった。
Unconcerned But Not Indifferent
無頓着、しかし無関心ではなく
これはマン・レイの墓碑銘に刻印された文言である。 続きを読む