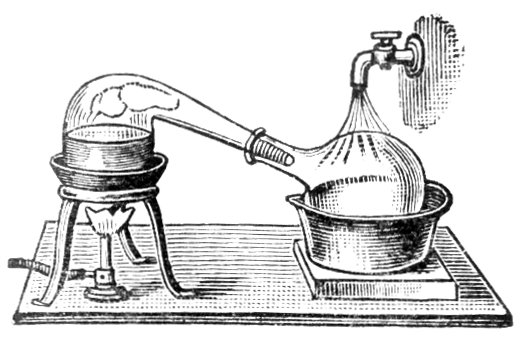dimensionsは薬品、治療法、医療機関、医療機器など医療関連固有名詞をキイとして、患者が体験した事実を可視化することをめざしている。現在、バグフィックス中であるが、追加機能や用途についていろいろなアイデアが浮かんできている。
薬品など固有名詞によって可視化されるのは患者が体験した事実だが、これはもちろん客観的な事実である。従来、患者体験は「闘病記」というパッケージで一括され、どちらかと言えば「作品コンテンツ」みたいに捉えられてきた。そうではなく闘病ドキュメントを闘病者が実際に体験した「事実」の集合体と捉え、それら事実群によって構成される「次元」を抽出することによって、医療現場で何が起きているかを可視化しようというのがTOBYOプロジェクトの基本的な立場である。
だが、客観的事実だけでなく、患者が体験した「主観的な事実」というものが一方には存在している。では闘病体験の中で最も重要な「主観的事実」とは何かと考えると、それはまず「痛み」だろう。「痛み」は唯一患者だけが体験する主観的事実である。そして実際に闘病体験ドキュメントにおいて、「痛み」について言及されることはきわめて多い。たとえば関節リウマチ患者の体験ドキュメントなどで、日々の痛みの頻度や程度が克明に記録されているケースをしばしば目にする。痛みの発生を時間表でマークしたり、痛みの程度を5ランクなどランキングや数値で表現したり、さまざまな主観的尺度が工夫され「痛み」の記録があちこちの闘病サイトで生成されている。痛みのほかにも、「気分、かゆみ、膨満感、吐き気」など多彩な主観的事実の記述は、闘病体験ドキュメントの多くの部分を占めているのだ。これらデータをどのように可視化し活用するかということも、dimensionsおよびリサーチ・イノベーションの大きな課題であると、最近になって認識し始めている。 続きを読む